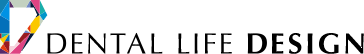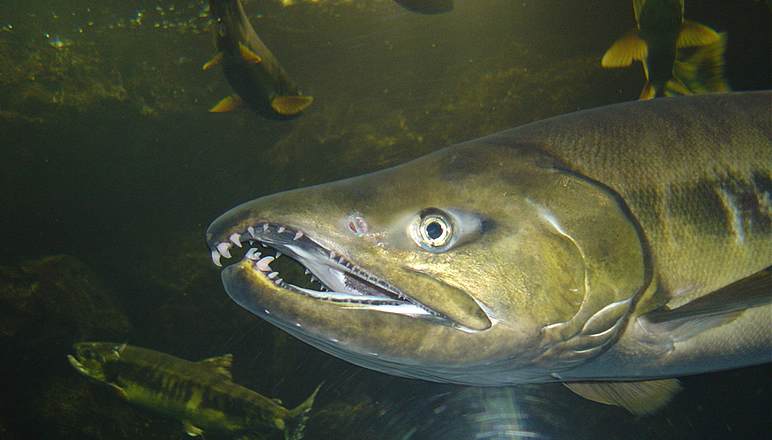乳幼児の齲蝕の減少について語る上で 忘れてはならないことがある。 それは、横浜臨床座談会の"むし歯予防研究会"の取り組みである。故丸森賢二先生を中心としたスタディグループで、さまざまな実践をたくさん発信された。 熱心な歯科医師がそれを参考にし、そのうねりが日本中に広がった。 我が国で齲蝕が減少したのは、この会の功績が非常に大きいと思う。 手元に、40年前に丸森賢二先生の講演会を聞いた時のメモがある。 そこには、以下のように書かれていた。
*「むし歯予防は、生まれた時の育児で始まる」 *「早期発見・早期治療(治療的アプローチ)ではなく、早期発見・早期指導(予防歯科的アプローチ)から始めなければならない」 *「歯科医学の真の進歩は、処置率を上げることではなく、罹患率を下げることである。乳歯の予防なくして永久歯の予防は語れない。」 そもそも1歳や2歳で齲蝕が多発する育児は正しいだろうか? 欲しがる時におやつを与えるなど、育児法に問題があるから齲蝕が発生する。 正しい育児は、そのまま齲蝕予防につながるはずだ。 だからこそ、"齲蝕予防は、生まれた時の育児で始まる"と言えるのである。 そう言えば、当時の興味深い話がある。 幼稚園の入園試験で齲蝕がないから合格したというものだ。 齲蝕があるのが当たり前の時代に、それがないのは、家庭がしっかりしていると判断され合格したのである。 さて、1975年(昭和50年)の3歳児のむし歯罹患者率は82.1%、6歳で97.3%であった(昭和50年歯科疾患実態調査)。 しかし当時、齲蝕の少ない集団があった。 家庭の事情で入所している児童養護施設(3~6歳児)の齲蝕罹患者率は60%だった。 さらに詳しく調べると、家庭から引き取られた小児の罹患者率は83.3%。 ところが、乳児院からの場合は24.3%と圧倒的に少なかった。 注1:乳児院は、保護者の病気や離婚などで養育できない0~3歳未満の乳幼児の施設。 そこで他の乳児院でも調査したところ、齲蝕罹患者率は4.8%だった。 しかも、乳歯の萌出前に入所したケースは、まったく齲蝕がなかった。 きっと、"甘い菓子を食べていない"・"菓子を買う予算の問題"などの理由と想像されただろう。 しかし、一般の小児と同じように食べていたのである。
唯一異なるのは、乳児院では、起床時間や就寝時間、食事や間食の時間などが決まっていたことだ。
徐々に規則正しい生活リズムが、齲蝕予防にとっても重要なことがわかってきた。 これが、"間食は時間を決めて与える"という指導につながっていく。 (石井欣一ら:幼児のう蝕免疫についての考察 ―乳児院における疫学調査―、紫耀、23(10)、1975.)
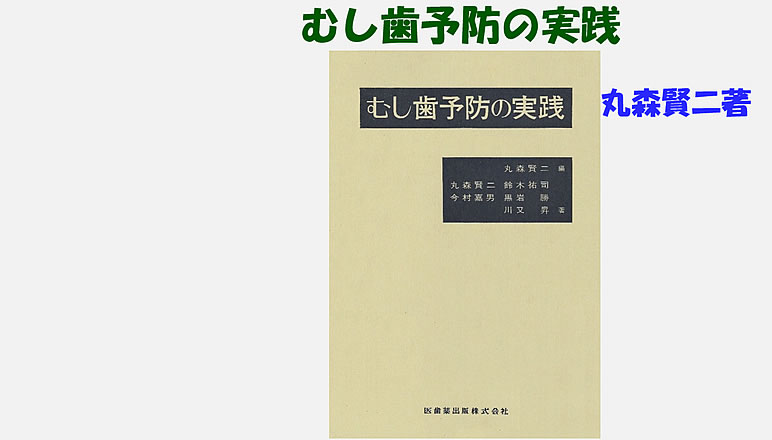
著者岡崎 好秀
前 岡山大学病院 小児歯科講師
国立モンゴル医科大学 客員教授
略歴
- 1978年 愛知学院大学歯学部 卒業 大阪大学小児歯科 入局
- 1984年 岡山大学小児歯科 講師専門:小児歯科・障害児歯科・健康教育
- 日本小児歯科学会:指導医
- 日本障害者歯科学会:認定医 評議員
- 日本口腔衛生学会:認定医,他
歯科豆知識
「Dr.オカザキのまるごと歯学」では、様々な角度から、歯学についてお話しします。
人が噛む効果について、また動物と食物の関係、治療の組立て、食べることと命について。
知っているようで知らなかった、歯に関する目からウロコのコラムです!
- 岡崎先生ホームページ:
https://okazaki8020.sakura.ne.jp/ - 岡崎先生の記事のバックナンバー:
https://www3.dental-plaza.com/writer/y-okazaki/