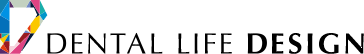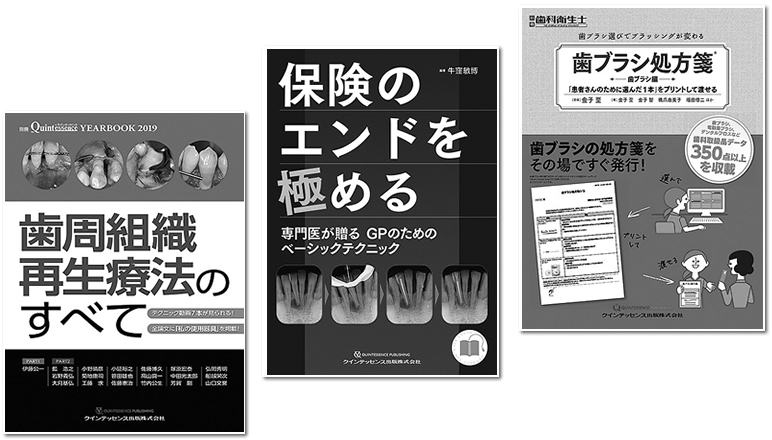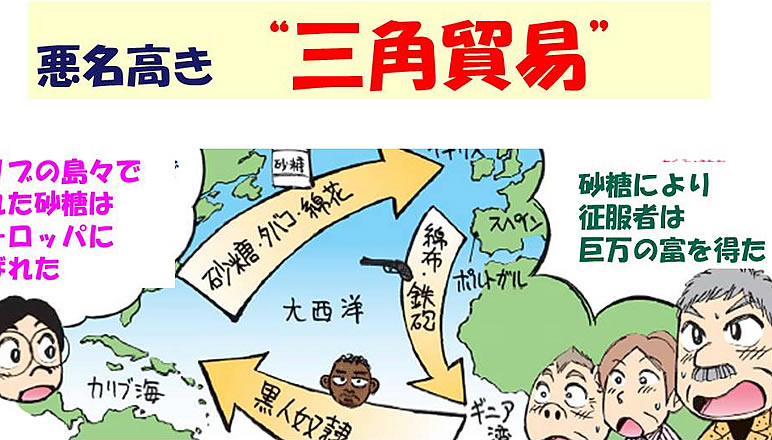ガミースマイルの診断・治療ステップが体験できるマニュアル本! ガミースマイル 11の要因 成功に導くトリートメントマップ
伝法昌広・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 15,400円(本体14,000円+税10%)・184頁 評 者 土屋賢司 (東京都・土屋歯科クリニック&Works) 私と本書の著者である伝法昌広先生との出会いは、20年ほど前にさかのぼる。 当時から物静かなイメージでありながらも、勉強熱心な青年矯正歯科医師であったのを覚えている。彼が以前より興味をもち続けている、「ガミースマイル」という題材をまとめた1冊ができあがった。 内面的な悩みをもち、審美的に改善を求める患者は多いが、ガミースマイルの原因やその改善方法は実は複雑で、奥が深い。 Dr. Frank Spearらは、ガミースマイルを 1. Short upper lip 2. Hyper mobile lip 3. Vertical and horizontal maxillary excess 4. Anterior over eruption 5. Wear and compensatory eruption 6. Altered active eruption 7. Altered passive eruption に分類している。 これらの7つの項目を大きく部位別に分けると、「口唇」「骨」「歯」「歯肉」の4パターンに分けられる。本書において筆者は、それらに関するガミースマイルの原因とその改善方法を矯正学的見地から考察し、「矯正歯科治療」「口腔外科」「歯周外科」「補綴治療」など、いずれかの治療オプションを単一、あるいは複合的に選択しながら、その治療ステップを提示しており、理解しやすい。 とくに成人の場合では、歯牙崩壊や欠損などが絡み合ってからのスタートであり、咬合、インプラント治療などをともなうため、やはり包括的な治療計画は必須であろう。補綴医と矯正医が連携して治療を施す際、もっとも基本となるのが上顎中切歯の位置を骨格、顔貌のどこに設定するかを共有することである。しかし、必ずしも骨格的な位置と顔貌的な位置とがマッチするとは限らない。そのような場合には、どこをエンドポイントにするのかを術前にディスカッションすることが大切である。ガミースマイル症例は、まさにその中切歯の位置決めをスターティングポイントとするケースであろう。 本書は、具体的な治療改善を豊富な症例から見ることで、読者も読みながら、それぞれカテゴリーの治療ステップを体感できる。いわば“マニュアル本”である。私も、著者とはいくつかのガミースマイル症例を連携しながら治療にあたったが、ガミースマイルが改善された後の患者の笑顔からは、人に言えない悩みを抱えていた術前とはまったく違い、思い切り笑える人生を得た喜びが肌で感じられた。それに治療を通して貢献できたことを感じられるのも、ガミースマイルの治療ならではであろう。 本書は、ガミースマイルで悩むすべての患者を治療しようと努力している読者にとって、必須な1冊になるだろうと確信している。
術式の詳説とノウハウ,成功のコツが詰まった天才からの贈りもの 硬・軟組織 マネジメント大全
石川知弘・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 19,800円(本体18,000円+税10%)・240頁 評 者 水上哲也 (福岡県・水上歯科クリニック) 世の中には「ギフテッド」と呼ばれる種類の人々がわずかながらも存在する。歯科界における「ギフテッド」と思しき人物は、著者の石川知弘先生をおいて他にいないと私はつねづね思っている。 これまでにも多くの講演や論文で数々の美しい臨床例を供覧してきた著者ではあるが、その技術やコンセプトの詳細を知る機会は多くはなかった。そのようななか,圧倒的な情報量を持った本書はまさに待望の一冊であると感じる。豊富な臨床例、卓越した文献的考察、そして臨床経験、臨床実感を織り交ぜたノウハウやポイントの解説は、まさに読者に対する「ギフト」であろう。 また、多くの海外の第一人者の臨床医たちと互いにリスペクトを持ちながら情報交換している著者ならではのプライベートオピニオンも大変貴重だ。具体的には、「圧力に耐えることができるか否か」や「舌房が大切」といったGBRの臨床のリアルな部分を織り交ぜて解説している点である。このようなコンテンツは今までの書籍にはない特徴であろう。 本書を読んで特に印象的であったのは、その鮮やかな臨床写真に圧倒されることである。「目は口ほどに物を言う」という慣用句があるが、歯科医療では「1枚の症例写真は多くを物語る」と言い換えてよいであろう。われわれはよくプレゼンテーションを見る機会があるが、慣れてくると一枚のスライド写真をみただけでその歯科医師の臨床技術や姿勢などの背景が見えてくるものだ。 たとえば、外科手術の1枚の写真を見ることで「この人の手術は痛そう」とか「おそらくだいぶ腫れただろう」など、その経過までも推測できる。そしてお節介ながら「患者さんは少ないのではないか」とか「経営が難しいのではないか」などと、そのクリニックの背景までも見え隠れする。驚くべきことに、本書における症例の写真はどれも美しく緊張感を有しており、その手技の芸術性に感銘を受ける。おそらく日々の膨大な臨床をこなしながらもつねに気を抜くことなく、そして新しい技術と改良を求めるがゆえに発する写真の緊張感なのであろう。 本書が膨大な量の情報が満載された書籍であることは間違いない。鮮やかな臨床例、膨大な文献、そして何よりも他の書籍にはみられない術式の解説とノウハウ、ちょっとしたコツなどが詳細に書かれている。ぱっと見はずっしりと重たそうに見えるが、ページをめくってみるとその内容の面白さと有益さに感動を覚える。複雑な術式や治療はややもすると敬遠されがちな昨今であるが、本書を熟読することで道が拓けていくような気がする。 これだけの臨床技術に到達した著者の硬・軟組織マネジメントも、本人に言わせると「いまだに改善の余地があり、進化し続けている処置」とのこと。これまで絶えず改良し続けてきた著者ゆえの名言かもしれない. 多くの方々がこの「ギフト」の恩恵にあずかることを願いたい。
実例で深める口腔機能低下症の理解とアプローチ 患者さんにしっかり説明できる 2 口腔機能“実践”読本 口腔機能低下症&口腔機能発達不全症 高齢者および小児の口腔機能を正しく理解し臨床に活かす
鈴木宏樹/松村香織・監著 安藤壮吾/相宮秀俊/押村憲昭/稲吉孝介/ 吉岡和彦/中尾 祐/馬場 聡/川西真裕美/吉村聡美・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 8,800円(本体8,000円+税10%)・152頁 評 者 松田謙一 (大阪府・ハイライフ大阪梅田歯科医院) 口腔機能低下症が病名として保険収載されてからすでに随分と経過しており、歯科医師の多くが高齢者の歯科治療にとって大切な分野であることを認識し始めているのではないだろうか。しかしながら、大学教育においては口腔機能低下症の診断や治療に関する専門的な教育が十分に整備されておらず、多くの歯科医師が卒業後に書籍やセミナーを通じて知識を補っているのが現状である。そのような状況のなか、本書は診断や治療の実践を支える、わかりやすく実用的な参考書として発刊された。 評者が感じた本書の「良いところ」を紹介したい。1つ目に、各項目の検査法だけでなく、訓練法についてもわかりやすく記されている点である。これまでの参考書の多くは検査法がおもに記されることが多かったように感じる。しかし、本書では各項目に対してどのようなトレーニングが有効かを表にまとめているため、治療方針やトレーニングプログラムの決定の際に非常に役立つのではないだろうか。 2つ目に、実例の充実ぶりである。第2章は「口腔機能に対する取り組みの実例から学ぶ」という章タイトルで、多くの先生方による症例が掲載されている。それぞれの先生方が自分なりのアプローチで、口腔機能をどのように改善したかを治療の経過とともに学ぶことができる。また、症例のバリエーションが非常に豊富で、部分床義歯や全部床義歯だけでなく、管理栄養士や言語聴覚士と連携した症例や、インプラント補綴、MRONJ(薬剤関連顎骨壊死)、矯正治療、嚥下障害など、多岐にわたっている。そのため、読者の専門分野を問わず、高齢者を対象に臨床を行っている歯科医療関係者であれば必ず勉強になる内容だといえる。 3つ目に、口腔機能発達不全症についても学べる点である。第3章には口腔機能発達不全症に関する章が設けられている。高齢者の口腔機能低下症と対をなす形で導入された口腔機能発達不全症であるが、普段から小児が専門でなければその臨床のポイントを知ることが難しいと考える先生も多いのではないだろうか。本章ではまさにそのような先生にちょうど良いボリュームで、わかりやすく書かれている。 4つ目に、切り離せる付録が付いてくる点である。この付録は本書の大きな特徴でもあるが、患者説明用に非常に便利な資料となっており、これだけでも購入する価値があるのではないだろうか。 本書は、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで、精力的に講演や執筆活動をされている鈴木宏樹先生と松村香織先生のお二人が監修され、また高齢者や小児の口腔機能の維持回復・向上に真剣に取り組みながら第一線で活躍されている多くの臨床家が執筆している。まさに、超高齢社会で高齢者の口腔健康と口腔機能を守る歯科医師にとって、時代を捉えた必読書であると最後に記しておきたい。
歯科医師と歯科衛生士で共有したいスタッフ向けIOS入門書・決定版! × みるみる理解できる 図解 スタッフ向けIOS入門
星 憲幸・監著 井上絵理香/川西範繁/北道敏行/ 鈴木美南子/藤﨑みのり/渡邊真由美・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 4,950円(本体4,500円+税10%)・124頁 評 者 小川勝久 (東京都・小川歯科・天王洲インプラントセンター) IOS(Intra Oral Scanner)とは、簡単に言えば「小さなカメラで口腔内の情報を得るもの」である。得られたデータは歯冠修復のみならず、近年では矯正歯科治療、外科手術、インプラント治療などに応用され、さらにはコミュニケーションツールとしてインフォームドコンセントやコンサルテーションなどに用いられてきている。ただ、スタッフ向けのIOS使用方法や活用例という点では、わかりやすくまとめた書籍はこれまでなかっただろう。 本書『別冊ザ・クインテッセンス×歯科衛生士 みるみる理解できる 図解 スタッフ向けIOS入門』は、イラストや臨床写真を用いてまさに“みるみる理解できる”よう、ていねいに解説した1冊である。 8つのパートで構成された本書は、まずPART 1「歯科におけるデジタルについて」で、デジタル化の歴史やデジタル用語、歯科におけるデジタル化の利用現状・重要性などを述べている。PART 2「IOSを理解しよう」では、IOSの基本知識としてさまざまなIOSを提示するとともに修復・補綴治療での有効性を取り上げている。また、IOSの活用場面や利点・欠点、使用時の注意点、修復・補綴治療、審美治療、インプラント治療での応用例までもを紹介している。PART 3は「IOSの準備」と題し、IOS操作にあたって理解しておきたいスキャンデータ構築のしくみや、データの歪みとその原因などもわかりやすく解説。また、周辺機器の整備としてパソコンのスペックや選び方などにも触れ、IOS導入を検討中の医院にとって非常に参考になる。 PART 4〜7はより実践的な内容となり、PART 4「IOSの操作」では、細かな事前準備や環境の整備、IOS操作時の注意点・操作方法をていねいに示している。PART 5「IOSの使用後の取り扱い」では、スキャンデータの後処理および変換作業の手順、さらにはスキャナーチップの消毒や滅菌方法等にも言及。そしてPART 6は、「歯科衛生士臨床におけるIOSの応用」である。IOSに慣れていない歯科衛生士でも実際の臨床の場で応用できるよう、初診時,印象採得時(スタディモデル用)、メインテナンス時などの活用例を紐解いている。つづくPART 7「修復/補綴・インプラント・アライナー矯正治療におけるIOSの応用」は、歯科医師による治療ではあるものの、アシスタントワークや口腔衛生指導にかかわるうえでスタッフも理解しておきたいことを、さまざまな症例をとおして解説している。最後のPART 8は、IOSの今後の展望についてである。 IOSが苦手な歯科医師やこれから導入する医院のスタッフにとっては、“まさにこんな本がほしかった”と言えるのではないだろうか。すでにIOSを活用している医院にも役立つ情報が紹介されており、デジタル化が進む今、各医院で常備しておきたい書籍である。
成人矯正治療における過蓋咬合への治療アプローチがわかる1冊 臨床家のための矯正YEARBOOK2024 成人の過蓋咬合を考える
クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 7,040円(本体6,400円+税10%)・176頁 評 者 竜 立雄 (福島県・RYU矯正歯科クリニック郡山プレミア) 本別冊がフォーカスした成人の過蓋咬合は、垂直的問題を有するため、不正咬合の中でも実は難しい矯正治療の1つである。 過蓋咬合を良好に矯正治療を行うためには、適切なオーバーバイトコントロールが必須である。セファロ分析など矯正診断の結果から、歯系では上下顎切歯の垂直的過萌出、挺出によるもの、上下顎臼歯の低位によるものが過蓋咬合の原因として挙げられる。また、過蓋咬合は深いSpeeカーブを呈しているため、矯正治療上、レベリングによる平坦化も難易度として高い不正咬合である。垂直的な骨格系の分析では、下顎角が小さくて下顎枝は長い、下顎下縁平面が平坦な「Low angle case」が特徴的に認められる。骨格形態に準じて側貌は短顔型で、いわゆる「Short Face」を示す。このような顎顔面形態をもつ場合、咬合力、咀嚼筋、口輪筋が強い傾向があると言われている。 過蓋咬合は、Ⅱ級、Ⅲ級不正咬合と併発して認められる不正咬合なので、前後的な問題と垂直的な問題の両面から診断を行い、戦略的な矯正治療のプランニングを立案する必要がある。過蓋咬合の矯正治療後の安定を考慮すると、上下顎切歯は確固な咬合接触を作ることが大切で、下顎切歯が舌側に後戻りすると切歯の過剰萌出が生じ、過蓋咬合が再発するため、下顎切歯の排列を維持することは、オーバーバイトを維持する上で重要である。 矯正治療には年齢制限はなく、デンタルIQの高まりから近年、矯正治療のニーズは拡大している。本書の巻頭トピックスでは、「成人矯正と歯周病─歯周-矯正治療の原則」というタイトルで“歯周治療の戦略において矯正治療は単なる歯の移動手段だけでなく、歯周組織の環境を改善し、歯周組織の長期的安定を導く歯周治療”の手段としての意義についてまとめられている。 特集の第Ⅰ部では、著名なスタディーグループによる症例提示が掲載されている。過蓋咬合の原因・診断に基づき、治療計画を立案し、治療を実践した素晴らしい症例が供覧されている。とくに患者の協力を必要としない歯科矯正用アンカースクリューを使用した前歯の圧下によるオーバーバイトコントロールと歯列の遠心移動による過蓋咬合の治療は、効率的な矯正治療の上で革新的で、もはや成人の矯正治療では必要不可欠な治療ツールと言っても過言ではないだろう。 特集の第Ⅱ部では、メーカーによる商品紹介&臨床紹介で、成人の過蓋咬合に関連した製品が記載されている。そのほか、第82回日本矯正歯科学会学術大会の事後抄録や海外学会レポート、フェイススキャナーの役割と続き、矯正治療のトレンドと今後がわかる内容となっている。 本書でふれている成人矯正における過蓋咬合への治療アプローチは、多くの患者さまのQOL向上につながるものと確信し、臨床的な書籍としてお薦めしたい1冊である。