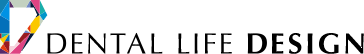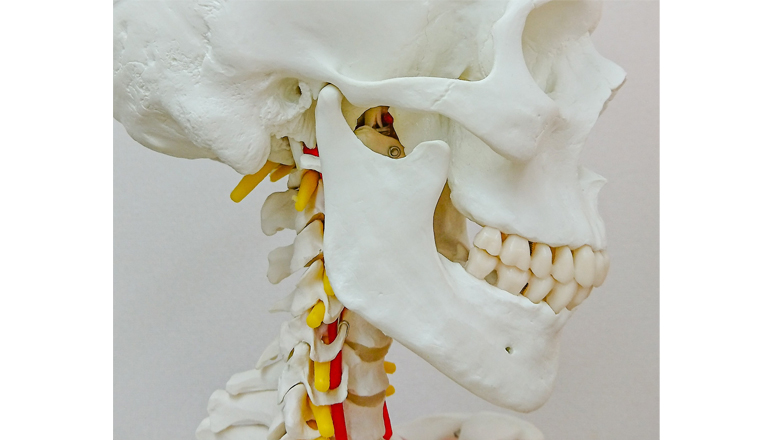近年、無歯顎患者は減少傾向にあり、若い先生にとっては総義歯治療に接する機会が減りつつあります。その一方で、難症例化が進み、総義歯治療へのニーズ自体も根強く残っているのが現状です。そうした中、過去には(株)モリタ主催の「吸着総義歯セミナー」の講師を務めるなど、安定して噛める総義歯テクニックの普及に尽力されてきた「くにみ野さいとう歯科医院」の齋藤善広院長に、総義歯の学びを深めた経緯や総義歯治療に取り組む意義を伺いました。宮城県仙台市 くにみ野さいとう歯科医院 院長 齋藤 善広 先生 <齋藤 善広(さいとう よしひろ)先生プロフィール> 1986年 岩手医科大学歯学部 卒業) 1990年 同大学大学院 歯学研究科 修了(歯学博士) 1992年 くにみ野さいとう歯科医院開設 2007年 臨床研修施設指定 070035 2010年〜2022年 (株)モリタ「吸着総義歯セミナー」主宰 2014年〜 岩手医科大学臨床教授
恩師との出会いから総義歯の奥深さに夢中に
-- 齋藤先生は長年、積極的に総義歯治療に取り組んでこられました。どんなことがきっかけだったのでしょうか 私は口腔外科出身だったこともあり、30数年前に開業したばかりのころ、総義歯を製作しても正しくできているのか、どこかで不安を感じていました。当然、大学では総義歯について学んではいるものの、それは「こうやって作りましょう」というプロセスの話であって、どんな総義歯を完成させれば正解なのかというゴールについては教わりませんでした。特に、教科書に載っていないような難症例を診る機会も多く、目指すべき義歯の姿を明確にイメージできないまま、製作していたように思います。 そうした背景がある中で、矯正治療の勉強会に参加する機会がありました。すると、理想の咬合や歯列、見た目とは何かを、それまで以上に考えるようになりました。総義歯治療では失われた咬合や歯列の再現を目指します。矯正治療も正しい噛み合わせや理想的な歯並びを目指す治療であり、共通する部分があるのです。ですから、最初は矯正治療を学ぶ一環として総義歯に興味を持つようになったのだと思います。 -- どのようにして総義歯の学びを深められたのでしょうか 昨年、亡くなられた大野健夫先生との出会いが大きかったと思います。彼は妥協のない技工物をつくる歯科技工士でした。印象採得や咬合採得の役割は、義歯製作において重要な情報をラボサイドに伝達することです。大野さんはとことんつくり込む人だったため、できあがった義歯にエラーがあれば、それは正しい情報を伝達できなかった私の責任なんです。だから、大野さんとのやり取りは常に真剣で、自然と技術のブラッシュアップにつながっていきました。 もう一つ大野さんとの出会いで大きかったのは、彼が考案した等脚台形法です。彼はどんな人工歯排列であれば正解なのか、歯科医師に聞いてまわったことがあるそうです。当時、その答えを明確に持ち合わせている歯科医師がどれだけいたのかはわかりませんが、多くの見解が「もともと歯があった場所がいいのではないか」というものだったそうです。では、無歯顎患者の模型からどのようにすれば、その場所を見つけられるのか。大野先生はそうした探求を続けていました。そうしてたどり着いた形が等脚台形でした。 -- 等脚台形法とはどんな考え方なのでしょうか 下顎の歯列弓の形は無歯顎になっても基本的には変わらず、骨吸収が起こると顎堤は下方に下がります。一方、上顎の顎堤は多くの場合、内側へ向かって吸収されるため、天然歯があった場所は上顎のほうが見つけづらくなります。そこで下顎模型を計測して等脚台形を求め、得られた等脚台形を上顎模型上に転写することで、上下歯列弓の大きさと位置を調和させやすくするという考え方です。 無歯顎における臼歯部の水平的基準は、従来よりパウンドラインでコンセンサスが得られています。しかし、無歯顎模型では前方基準点が存在せずに曖昧になることなどから、パウンドラインだけでは不十分です。そこに等脚台形法が加わったことで患者固有の水平的基準が見つけやすくなりました。大野建夫先生が考案された「等脚台形法」 -- 下顎総義歯の吸着を理論構築された阿部二郎先生とは、どのように出会われたのでしょうか 自分なりに工夫をしながら総義歯製作をしていたころ、義歯の大家と呼ばれる先生に誘われて阿部二郎先生の勉強会に参加しました。それが最初です。阿部先生による「Frame Cut Backトレー」(FCBT)を用いた下顎総義歯の吸着テクニックは教え通りに実践すると、本当に吸着し、とても驚きました。 「FCBT」とはレトロモラーパッドなど、封鎖にとって重要な部分のフレームを取り除いたスナップ印象用トレーのことで、印象材には歯科用アルギン酸塩印象材「アルフレックスダストフリー」と「アルフレックスデンチャー」を使用します。そして、無圧的に操作することで、粘膜の折り返しがありのままに採得されます。この無理のない自然な印象採得によって、熟練度に関わらず、吸着にとって不可欠な義歯床辺縁の全周封鎖が獲得できるようになります。 先ほど、大学ではプロセスしか教わらなかったと言いましたが、吸着総義歯を知ったことで、吸着することが目指すべきゴールのひとつであり、義歯の姿としてのひとつの正解なのだと知れたことは大きな収穫でした。
阿部二郎先生による「Frame Cut Backトレー」。無理のない自然な印象採得によって、吸着にとって不可欠な義歯床辺縁の全周封鎖が獲得できる。
若い先生が総義歯を学ぶ意義とは
-- あらためて、現在の無歯顎患者の状況や総義歯治療に関して思うことがあれば教えてください 歯周治療の発展や国民的な予防意識の高まりから、現在、無歯顎患者は減少傾向にあり、都心部ではあまり見かけなくなりました。また、若い世代ほどDMF指数が低く、人口動態から考えても今後、無歯顎患者はさらに減るものと思います。ただ、厚生労働省の「歯科疾患実態調査」によれば、80〜84歳の総義歯患者の割合は約3割で、85歳以上になると約4割にものぼります。地方ほど総義歯治療のニーズは根強く残っているのが現状です。また、寿命が延伸し、長寿社会と言われる現在、高度に顎堤吸収が進んだ難症例が増え、逆に難易度は高まっているようにも思います。 無歯顎患者の減少から大学でも臨床実習で触れる機会が減り、若い先生の中には総義歯に苦手意識を持っている方も多いと思います。必ずしも、すべての先生が総義歯を得意としなくてもいいと思いますが、難症例であってもきちんと対応できる若い先生が各地域で育って欲しいと思っています。 -- 若い先生が総義歯を学ぶとしたら、どんなところに意義があるのでしょうか 良い総義歯とは何かを考える時、患者さんが喜べばいいのかというと、それだけではありません。もちろん、それも大事ではありますが、いちばんは審美的にも機能的にも優れた義歯だと考えています。では、どんな義歯ならそのように評価できるのか。それには良し悪しを数値化し、客観的に判断することだと思います。そのためにもゴシックアーチ描記法や咀嚼機能検査などで得られるデータを私は重視しています。 長年、そうしたデータを見ているうちに、結局のところ、私がやっていることは平均値を出すことなんだと、はたと気づいた瞬間がありました。総義歯製作では全顎的な咬合再構成を行う中で、あらゆる形態的な評価を平均値の範囲内に収まるように考えます。そのうえで症例ごとに歯科医師としての裁量をどう入れ込み、整合性を崩さないような改変と選択を行って個別化を図るのか。総義歯治療は究極の平均値の探索みたいなところがあります。 そうした探索を続ける中で理想的な咬合や歯列、下顎位への理解が深まり、生体のファジーさを含め、口腔の全体像をつかむことにつながったと思っています。それらのことがつかめると、部分床義歯やインプラント補綴など他の領域にも応用ができ、それは歯科医師としての財産になったと感じています。そうした点からも総義歯に興味を持つ若い先生が増えると嬉しく思います。インタビュイー 齋藤 善広(くにみ野さいとう歯科医院 院長) →吸着総義歯の普及に尽力されてきた齋藤善広先生に聞く、「KEEP 28」の考えと予防歯科にたどり着いたワケ<Part2>はこちら
TOP>コラム>吸着総義歯の普及に尽力されてきた齋藤善広先生に聞く、「KEEP 28」の考えと予防歯科にたどり着いたワケ<Part1>