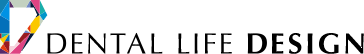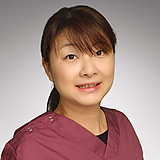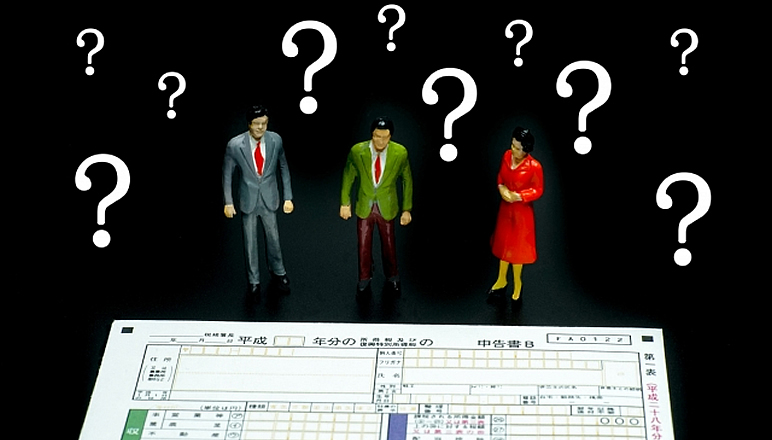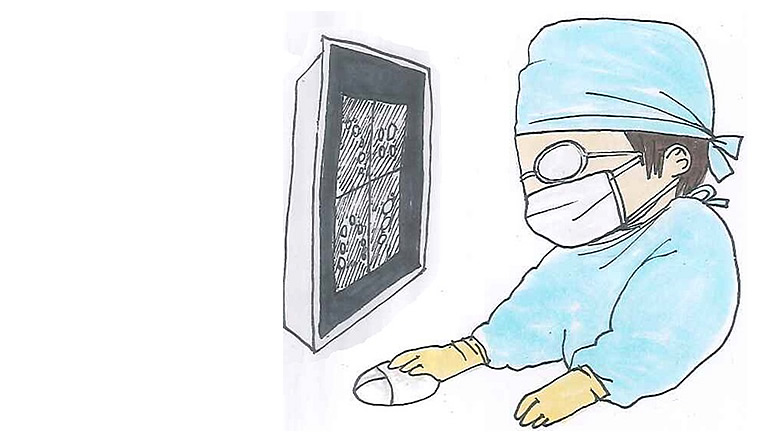皆様はどうして、
歯科衛生士になったのでしょうか?
「アニメの声優になりたい」
高校2年にもなって、そんな夢を持っていました。
クラスの仲間はみな大学進学に向けて本格的に勉強をしている時期です。
あきれた父が毎晩のように目の前に私を座らせ「声優だなんて、それで食べていけると思うのか?まともに進学を考えたらどうだ。」と諭しました。
隣で聞いていた母が「女性はね、結婚をしたらそれまでどんなに良い会社に勤めていたとしても、また1から働くのはとても難しいもの。
資格を持っていると、子育てが終わってからもまた働くことができる。
私が充実した日々を送れるのも、自分を持てるのも、資格があるからこそなのよ。」
母は好きな着物から着物の師範になり、更には和文タイプからワープロの先生にまでなり、
高校や専門学校で教えていました。
70代の今でも着物を生かした仕事を持ち、収入もあります。
そんな母が、「歯科衛生士」という資格があるから、どうか?と話を持ってきました。
どうやら知り合いの娘さんが歯科衛生士になったとのことでした。
「しかえいせいし」歯を衛生にする人?
遅ればせながら、担任の先生に進路相談をしました。
どうせなら、大きな病院がある学校へ入りたい!よくわからないけど、
その歯科衛生士ってものになって資格を取ろうじゃないか。
都会のど真ん中で学ぼうではないか!
都会のど真ん中の学生になると、今度は部活の歯学部学生が救急蘇生の授業があると教えてくれました。
興味のある私は歯科衛生士の授業を抜け出して、歯学部学生の授業を受けました。
見つかった!怒られるかと思いきや、「面白い奴だな」そして、私は大学病院の麻酔科に勤務しました。
更にはなんとスウェーデンからブローネマルク先生がやってきて、インプラントと出会うことになります。
日本で初めて、インプラントのアシスタントワークを伝授することになったのです。
なんでも知りたい!スウェーデンに行ってくる!意欲満々の日々です。
月日が流れ、結婚、出産となるうちに現場を離れることになります。
子供を公園に連れて行くようになります。
新たな社会です。
公園ママたちは過去にいろいろなお仕事に就いていました。
有名女子大学を出て一流企業にいた方、銀行に勤務していた方、
バスガイドだった方、キャビンアテンダントだった人などもいました。
でも、今はみな、同じ「~ちゃんのママ」なのです。
ママになると、なぜか旦那さんの土俵で話をするようになります。
旦那さんが何をしているかでママの評価になっていくのです。
「このママたち、自分の子供が何ができる、旦那が何をしているという自慢もいいけれど、
自分は何ができるということを何一つも言えないのではないか?」
子供が成長すると時間ができて、ママたちは働くことを考えます。
しかしそこには大きな壁がありました。
過去の栄光があっても「今何ができますか?」に応えることができないのです。
「私は・・私は歯科衛生士です。」
子供が大きくなると、自分の時間がたくさんでき、臨床現場で働く日々となりました。
若者歯科衛生士と一緒になり、医院の一員として働きます。
歯がなければ、食事が摂れません。話すことも食べることも、笑顔もなくなります。
食事が摂れなければ、健康な生活が送れません。その健康の入り口ともなる口腔内の健康を
守り、管理するのが私たちの役割です。
う蝕や歯周病にならないように、予防をする。
う蝕になってしまったら、修復をする、歯周病から守る、
欠損歯にインプラント治療を行う、口腔内の癌をいち早くみつけて、命を守る。
そんな重要な役割があるのが、私たち歯科衛生士のお仕事です。
募集に「40歳まで」なんて表記のある仕事と違い、その人生経験があればあるほど生きる仕事。だから60代の方でも生き生きと働き続けられる仕事です。
歯科衛生士になるまでが勉強ではなくて、歯科衛生士になってからが本当の勉強です。
自らの学びを止めないこと、常に新しい情報を取り入れていくこと。
子供たちにも「ママも勉強しているんだよ~」と言ってきました。
自分の世界があるからこそ、子供の世界も尊重できるのです。
人と人との繋がりの中で、その「人」の健康を守る素晴らしい仕事です。
女性が資格を持つことを教えてくれてた母には感謝しています。
え?アニメの声優の夢はあきらめたかって?
いえいえ、その夢はまだまだ持っていますよ・・今は、歌のおねぇさん♪になりたいです。
関連記事
Vol.1「歯科衛生士ってどんな仕事?」資格があるのは素晴らしい!
Vol.2「魔法の箱」
Vol.3「裸の王様」の物語
Vol.4「間違いを探せ!」おかしなHP
Vol.5「人とのつながり」
Vol.6「挨拶のできない子供たち」コミュニケーション不足の若者たち
Vol.7 臨床におけるジェネレーションギャップ