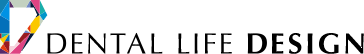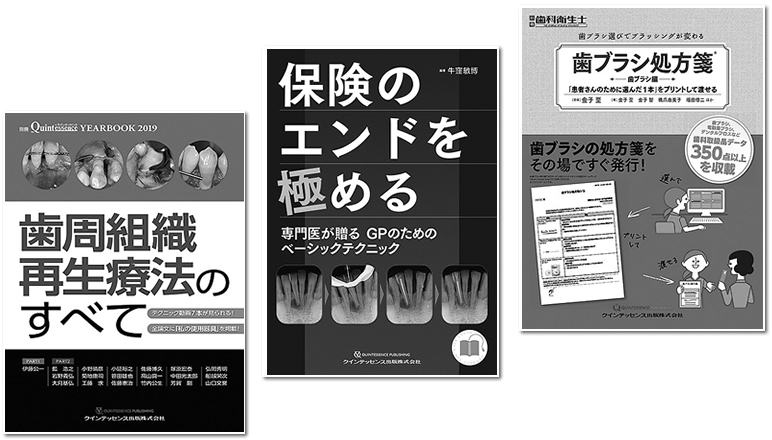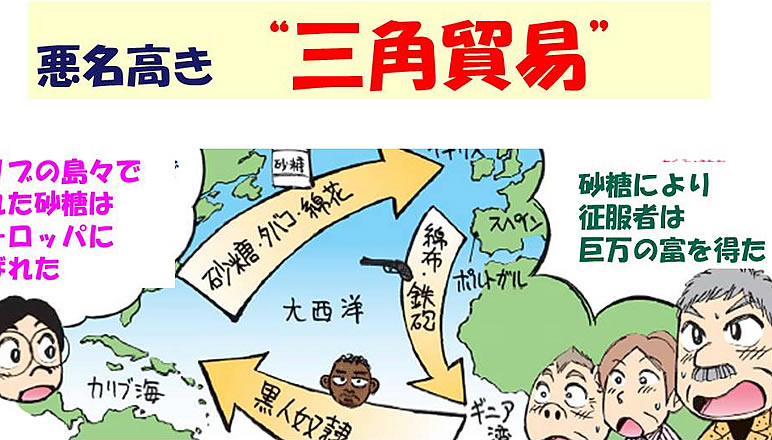5-Dのスゴさがわかる! 若い歯科医師たちの“道しるべ”となる1冊! 5-Dコンセンサス 歯の保存にこだわる これまでの軌跡と次世代へのメッセージ
石川知弘/北島 一/福西一浩/ 船登彰芳/南 昌宏・監著 藍 浩之/石川 亮/片山明彦/ 菊地康司/丹野 努・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 29,700円(本体27,000円+税10%)・480頁 評 者 水上哲也 (福岡県・水上歯科クリニック) 周知の通り、5-D Japanは長きに渡り日本の歯科界をリードしてきたグループである。ファウンダーは評者と同世代で、わが国の臨床医のリーダーとして、啓発者として尊敬すべき歯科医師たちである。 本書は2,000枚を超える膨大な量の症例写真と500ページ近い分量で5-Dコンセンサスに基づいた質の高い臨床の実践とその理論、ノウハウが収載されている。大著にもかかわらず、臨床例も内容もまったく隙がなく、緊張感に満ちた内容になっているところは流石である。執筆中の著者たちのお互いの叱咤激励の声が聞こえてくるようである。それぞれが卓越した専門分野をもつことで、各分野において深い知識と臨床を提示できることがグループ活動の最大の強みだとあらためて感じさせる。 本書は一気に読み込むことは難しいが、各Chapterが1冊の本のようにまとまっているため、読者にはChapterごとに日にちを分け、じっくり読むことをお勧めしたい。 石川先生、北島先生は誰もが認める再生療法における天才的な臨床医である。その技術は繊細であり、また芸術性に満ちた才能を感じさせる。今後十数年、この2人を超える臨床医は出てこないのではないか。 福西先生の臨床は自分に厳しく、患者に優しいものであると感じる。先生が勤務医時代から師匠の下で培った知識や技術をさらに自身の工夫や努力で発展させ、自身の臨床を集大成させたことは実にすばらしい。 船登先生は本書では切除療法を担当されたが、切除療法からファイバーリテンション、再生療法に至るまでの歯周治療に対する考え方の変遷が示されていることが興味深い。また、巻頭言では他のメンバーに対する友情や想いがよく伝わってくる。 南先生によるマイクロスコープの解説はわかりやすく、初心者にもアドバンスな読者にもためになる内容で書かれていることが流石と感じる。先生はいつも他の追随を許さないほど優れた見識をもち、鋭い視点からの考察は秀逸で、その臨床はもはや哲学的とさえ感じることがある。 また、ファウンダーに続く次世代を担う5名の著者陣は、いずれも優秀な逸材でかつ精鋭である。オールラウンドにすべての臨床をこなし、それぞれが師事する歯科医師の薫陶を受け、さらにその分野について深く追求しようとされており、今後さらなる活躍に期待したい。 本書はファウンダー5名が長年にわたって歩んできた“道”を示すものと感じられた。“道”によって新しい街ができ、人びとが集まり、往来は栄える。一方で、“道”によって古い街が廃れ、しばしば歴史のなかに埋もれてしまうことがある。しかし、広く整然と区画整理された“道”は長きにわたり人びとの生活を支え続け、今日に至っていることは間違いない。そのようなことを考えながら本書を拝読させていただいた。 本書が今後長きにわたり、やる気に溢れる若い歯科医師たちの“道しるべ”となることを願いたい。
マイクロスコープの所有だけでは満足しない志の高い先生方の意欲に応える書籍 別冊ザ・クインテッセンス マイクロデンティストリーYEARBOOK2025 歯科医師&歯科衛生士が活用できるマイクロスコープ下の臨床テクニック
別冊ザ・クインテッセンス マイクロデンティストリーYEARBOOK2025 歯科医師&歯科衛生士が活用できるマイクロスコープ下の臨床テクニック 日本顕微鏡歯科学会・編 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 6,380円(本体5,800円+税10%)・152頁 評 者 和達礼子 (東京都・マンダリンデンタルオフィス) マイクロスコープが日本の歯科臨床に登場したのは、30年ほど前になる。今では卒前教育で学生が触れる機会もあり、新規開業する先生方にとっては、もはや必須のデバイスであろう。ベテラン世代でも、ご子息、ご息女が購入し、「自分もはまってしまった」とうれしそうに話される先生によくお会いする。 さて、日本顕微鏡歯科学会(JAMD)は、マイクロスコープを用いた歯科治療を牽引している学会である。現在もっとも若手歯科医師を引き付けている、勢いのある団体の1つであることは間違いない。本書は、その日本顕微鏡歯科学会が編集し、毎年刊行している別冊の2025年度版である。 PART1“New Topics”では、学術大会での講演が掲載されている。シンポジウムで講演された名古屋大学大学院名誉教授の鈴木繁夫先生は、マイクロスコープ使用における“直視派”と“ミラー派”とを、歯科とは異なる視点で分析されており、日頃マイクロスコープを使用している評者としても目から鱗の内容であった。また、大会長賞を受賞された野亀慶訓先生、最優秀ポスター賞を受賞された樋口敬洋先生は、評者には永遠にできそうもない見事なコンポジットレジン修復を、だれにでも簡単にできるのではないかと錯覚させるほどのわかりやすい写真を惜しげもなく用いて解説されている。 PART2では“マイクロスコープUp-to-Date”と題し、三橋晃先生が韓国のマイクロスコープ臨床の最新情報を、北村和夫先生、柴原清隆先生、大河原純也先生らは学会誌MICROに掲載された論文を紹介されている。診療室を飛び出し日本から世界へ発信されている先生方の意欲に、おおいに刺激を受ける。 PART3はケースプレゼンテーションとなっており、サージカルガイドを用いた自家歯牙移植、精巧なプロビジョナルレストレーションを用いた審美修復治療、テープストレージを使用したデータ管理は、同じ歯科医師を名乗るのが恥ずかしくなるほどのハイレベルである。また、歯科衛生士による2本の論文は、今後の歯科衛生士業務の広がりを予見させ、スタッフのモチベーションアップに役立ちそうである。 PART4では、各社のマイクロスコープの最新情報、それらを用いた症例が提示されている。マイクロスコープを使用しているだけで、精密治療の最前線にいるかのような気分になっていたことが間違いであることに気づかされる。 マイクロスコープを持っているか、持っていないか、という時代はいずれ終わるだろう。多くの歯科医院が標準装備するようになった時、他と差別化するにはこれまでの研鑽が問われることになる。本書は、所有するだけでは満足しない、志の高い先生方の意欲に応えるものである。学術大会に参加された先生はその余韻を反芻し、そうでない先生はその熱気を感じ、さらなる高みに誘われることであろう。
アライナー矯正初学者はもちろん、実践している先生にとっても必携の書 アライナージェネレーション Dr. 尾島賢治のテクニック&分析ポイント131のすべて
尾島賢治・監著 檀 知里/渡邉仁資/熊谷友理子・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 29,700円(本体27,000円+税10%)・368頁 評 者 菅原準二 (宮城県・矯正歯科菅原準二クリニック) 著作においても、講演においても、そこには3つの“I”が含まれていることが重要だ。3つの“I”とは、すなわち第1にImpressive(印象的)であること、第2にInformative(有益)であること、そして第3にInteresting(興味深い)であることだ。本書の内容は、まさに3つの“I”に満ち溢れているというのが率直な読後感であったことを最初に述べておきたい。 さて、筆者が思う本書のキーワードは4つあり、それは【覚悟】【斬新】【道標】、そして【満腹】という言葉で表現できる。 【覚悟】:著者が15年前にワイヤー矯正を離れ、アライナー矯正に完全特化した臨床に転換したことを知り、その先見の明と不退転の覚悟に畏敬の念を抱いた。Dr. Werner Schuppという素晴らしいメンターと著者との出会いによって今日の道が開けたとは言え、アライナー矯正に特化する覚悟を決めたことに脱帽するしかない。 【斬新】:本書の第一印象は“斬新”という言葉に尽きる。これまで数多くの教科書に触れてきたが、全ページ黒地に白文字という装丁にはお目にかかったことがない。これでは余白に書き込みができないという思いもよぎったが(笑)、何とも鮮やかで美しい。加えて、随所に“動画でチェック”の二次元コードが配置され、何と本書がYouTubeとリンクしており、YouTuberでもある著者の豊富なコンテンツに触れることができるという重層的構造になっている。 【道標】:アライナー矯正の進歩は目覚ましく、外注型アライナー中心の第3世代から、内製型アライナーの第4世代に入り、さらに最近では第5世代と呼ばれる内製型形状記憶アライナーが出始めている。本書のタイトル『アライナージェネレーション』と決めたのは、そのような世代の変遷についても読者に伝えたいという著者の気持ちの表れであろう。本書という船には第3世代から第5世代までのアライナー矯正が乗り合わせており、著者はその識別に苦慮したと思われる。本書は奇しくもそのような世代の移行期に上梓されたことから、これからのアライナー矯正の進むべき方向を示す道標としての役割を果たしていると言えよう。 【満腹】:内容的には、矯正治療には欠かせない基本的な検査・診断の方法に始まり、不正咬合の症型別に数多くの治療例が詳細に提示されているだけでなく、アライナー矯正では難しいとされてきた抜歯症例の数々、成人期のみならず小児期からシニア期に至るまで年代別の使い分けに至るまで多彩だ。加えて、読者が思い浮かべると思われる質問に対する答えまで用意されているという周到さで、消化しきれないほどの満腹感を覚えた。 著者は、まぎれもなくアライナー矯正の世界的トップランナーの一人であり、本書は今後のアライナー矯正の大いなる進化に期待を抱かせてくれる。