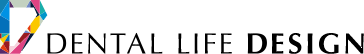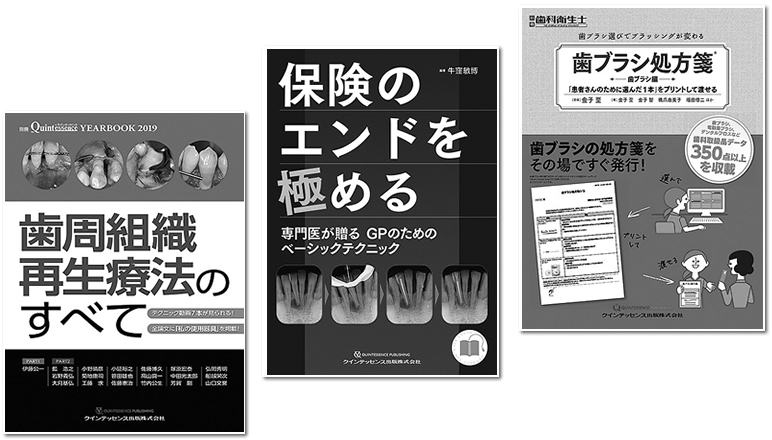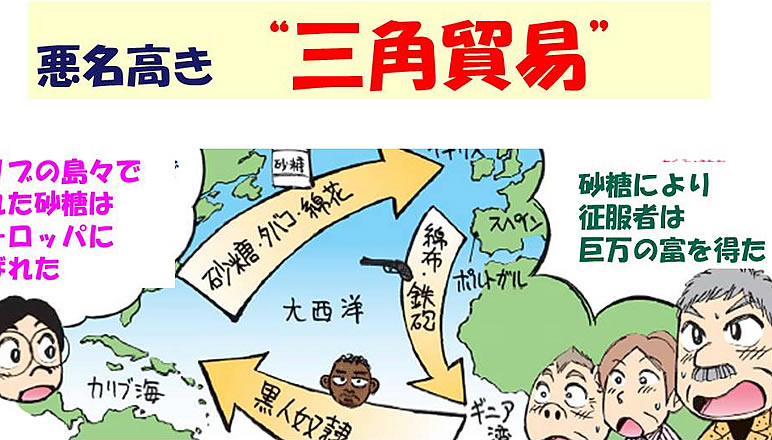混沌としているMRONJへの対応をまとめた最新の一冊 薬剤関連顎骨壊死 ビスホスホネート・デノスマブ投与患者に対する日米の最新の指針(2022・23)を踏まえた対応の実際
柴原孝彦/岸本裕充/矢郷 香/野村武史・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 7,920円(本体7,200円+税10%)・132頁 評 者 小林隆太郎 (日本歯科大学附属病院・病院長) 待望の書籍を手にすることができた。本書は、すべての臨床医にかかわり理解しなくてはならない「薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)についての課題」の最新の内容を取り扱っているからだ。AAOMS(米国口腔顎顔面外科学会)の2022年版ポジションペーパーと日本の2023年版ポジションペーパーを踏まえつつ、一般開業医を主な対象として、MRONJ対策についてわかりやすくまとめられている。 筆者自身、読み始めると止まらなくなった。というのも、これまで抱えていた多くの疑問が本書によって次々と解消されていったからである。 MRONJの発症を簡潔に表現すると、骨吸収抑制薬を投与されている患者において、口腔衛生状態の不良や歯性感染症の存在、さらに不適切な侵襲的歯科治療といった要因が重なった場合に発症することが多いと考えられる。しかしながら、臨床現場では歯科医師間で統一された見解のもとに診療が行われているとは言い難い。まずは正しい知識をもち、その理解に基づいてMRONJの予防に努めることが肝要である。 また本書の特徴の1つとして、急いで確認したい・絶対に知りたいことをすぐに役立てられるよう、「MRONJクイックレファレンス」が設けられている。これにより目次と連動して、必要な情報へ迅速にアクセスできる。MRONJについて疑問だらけであった筆者でも、ストレスなく理解を深めることができた。 ここで筆者がオススメする本書の読み方を紹介したい。まず、「CHAPTER 1 MRONJ(薬剤関連顎骨壊死)の概要の薬剤関連顎骨壊死にまつわる7つの疑問」の内容をご確認いただきたい。簡潔に疑問に対する回答が得られる構成となっており、本書の利用価値を大きく高めている。詳しくは本書をお手に取っていただければと思うが、これらのタイトルを見るだけでも、MRONJの核心に踏み込んでいることがわかる。 さらにCHAPTER 2では基本的な内容が整理されており、CHAPTER 3から6では、MRONJの症例を直接経験していない先生でも、誌上で数多くの症例に触れることができるため、その特徴を明確に把握できる構成となっている。 医学書には、知識を得るためのものや専門性を深めるためのものなど、それぞれ異なる目的がある。しかし本書は、臨床医として絶対に知っておくべき内容である。変化し続ける医療知識を学ぶうえで、個人的な卒後研修の一環としても、非常に重要な書籍と位置づけられる。 最後に、本書を通じてこれまでの疑問に対して最新の正しい知識を得ることができたことを、いち臨床医として心から感謝申し上げたい。このような有益な機会を与えてくださった柴原孝彦先生、岸本裕充先生、矢郷香先生、野村武史先生に、この場を借りて深く御礼申し上げる。
アライナー矯正治療を、戦略的に設計すべき治療としてとらえ直す必読書 アライナー矯正治療戦略 メカニクスから考える治療を成功に導く戦略体系
牧野正志/吉野智一・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 18,700円(本体17,000円+税10%)・224頁 評 者 米澤大地 (兵庫県・米澤歯科醫院) アライナー矯正治療が「患者ウケ重視」「誰でもできる簡便な治療方法」として、商業主義的に扱われてきた時代はそろそろ転換点を迎えているように思う。そしてブラケット・ワイヤー矯正治療を熟知し、力学に基づいて設計・実行できる矯正歯科医を「オルソドンティスト」と呼ぶように、これからはアライナー矯正治療を扱う歯科医師ならば、治療を戦略的に設計・実行できる臨床家、言うなれば「正統派アライニスト」としての視点が求められるであろう。 評者は、ブラケット・ワイヤー矯正治療を中心に全国の一般歯科医(GP)の先生がたとともに学び、実践してきた。そのためか、自分の周辺ではアライナー矯正治療について「メーカー主導」「口腔内スキャンをした後は歯科医師のすることはない」、そして「結果的にうまくはいかない」という先入観がいまだに根強く残っているのが現実である。しかし本書を読んで実感したのは、アライナーこそ、術者が矯正力の方向と治療段階を正確に読み、戦略的に設計する能力が求められる治療法だということであった。 本書は全2章構成で、アライナー矯正治療に必要なメカニクスの理解と治療戦略の構築力を、段階的に高めていく構成になっている。 Chapter1では、❶力学(「押すという移動方法」)・❷モーメント(「コントロールされた傾斜移動」)・❸固定源(「固定源(アンカレッジへの配慮)」)・❹矯正力の種類(「アライナー装着により加わる断続的な力」)・❺ステージング(「シームレスなステージング」)という5つの観点から、診断から治療の設計、実行までの流れが具体的に整理されている。メーカーのマニュアルや提示されたバーチャル治療計画をそのまま踏襲する操作ではなく、臨床歯科医として治療計画に臨む姿勢が一貫して語られているのが印象的である。 Chapter2では、非抜歯治療、Ⅱ級不正咬合、Ⅲ級不正咬合、上下顎小臼歯抜歯治療など実際の症例を通して、アライナーの適応と限界、さらには開咬・過蓋咬合などにおけるバーティカルコントロールの可能性についてもふみ込んでいる。特に、フィニッシングやリカバリーといった後半の悩ましい治療工程でどう立て直すか、場合によってはワイヤーとの併用をどう判断するかという現実的な判断軸が示されており、臨床家としての姿勢を正される内容である。「ブラケット矯正治療の研修は不要か?」という問いに対する著者の答えも印象的で、「No」であった。アライナー矯正治療を深く理解するには、力の作用点やモーメントといったメカニクスを学ぶ必要があり、またリカバリーの手段としてワイヤーをもたずに治療に挑むことは、無防備といわざるを得ない。 本書は、アライナー矯正治療を「便利な道具」などではなく、「戦略的に設計すべき治療」としてとらえ直すための必読書である。臨床に責任をもちたいすべての歯科医療従事者に、強く推薦する。
一般臨床を補完する矯正を取り入れて、治療の質を上げたい先生にお薦め LOTを知る 考え方とその実践
加治初彦・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 11,000円(本体10,000円+税10%)・120頁 評 者 弘岡秀明 (東京都・弘岡歯科医院) 近年、部分矯正や限局矯正をLOTと呼ぶことが一般的になってきたようである。少し前まではMTM(Minor Tooth Movement)と呼ばれていたこの分野がなぜLOTと呼ばれるようになったのかがよくわかる本である。 歯周病専門医となるべく筆者はスウェーデンで5年を超える留学生活を送っていた。そこにはエビデンスに基づいた正しい診断と的確な治療のもとで、重度の歯周病患者でも多くの歯が保存できる現実があった。 感染のコントロールが終了した後も歯周組織の脆弱化により病的な移動を起こしている歯が、その後のインプラントや欠損補綴を困難にしているケースにしばしば遭遇した。歯周病患者での矯正治療の必要性を強烈に認識させられた瞬間であった。 歯周病をもつ口腔内で病的に歯が移動している現象をPTM(Pathologic Tooth Movement)と呼ぶが、著者はこの分野を大きく3つに分類している。具体的には、 ①側方歯群の近心傾斜、 ②下顎前歯のクラウディングと挺出、 ③上顎前歯のフレアリング である。 PTMの観点から、歯周病専門医も矯正に関する知識は必須であると思っている。中等度以上の歯周病患者では、感染のコントロール終了後、残存歯をすべて移動するような矯正治療を行うことも多い。このような矯正は、決してマイナーな矯正とはいえないことから、著者は“多数歯のLOT”と呼び、従来からいわれているMTMや、全顎矯正(COT:Comprehensive Orthodontic Treatment)と明確に区別している。 GP(General Practitioner)が臨床のなかで、自ら矯正に取り組みづらい理由があるとしたら、1つは矯正の診断系がわかりにくいこと、もう1つがエッジワイズのメカニクスがわかりにくいことではないだろうか。本書は診断系についてはとてもわかりやすく、またエッジワイズについても、とくに現在広く使われているストレートワイヤーも含めた解説もていねいである。 LOTの診断はあくまでもCOTの診断を理解した延長上にあるという著者の信念が表現されていると思われる。ペリオ、エンドから補綴修復インプラントまでGPが臨床で行う治療範囲は非常に広い。あるGPは可撤式装置で混合歯列期の治療を行っているかもしれない。また違うGPはエッジワイズやアライナーで自らCOTを行っているかもしれない。しかし、これらの矯正は、矯正のみで完結する治療であることが多く、GPの他の分野を補完する矯正ではないことが多い。 GPが自ら矯正臨床を取り組むにあたってまず行うべき矯正は、ペリオや補綴、インプラントを補完する分野であるLOTだとする著者の主張には大いに賛同したい。一般臨床を補完する矯正を取り入れて、治療の質を上げたいと思っている先生にお薦めの本である。
超入門という表題の高度なオーバーレイ修復の教科書! オーバーレイ修復 超入門
辻本真規・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 9,900円(本体9,000円+税10%)・144頁 評 者 菅原佳広 (新潟県・月潟歯科クリニック) 明らかにう蝕罹患率が低下した現代においても修復治療の需要は高く、日々の臨床のなかで高頻度に行われている。従来の修復治療は、う蝕の罹患範囲を前提としたインレー、アンレー、部分被覆冠、全部被覆冠といった金属を用いた修復法が中心であり、ごく一部の範囲であれば、直接法の充填という考え方だったと思われる。 これに対し、修復材料が進化し接着修復が確立していくにつれ、修復物の都合で大きく歯質を削除することを反省する概念(Minimal Intervention)が定着した。とくにコンポジットレジン修復の発展により、かなり大型の窩洞形態においても直接法が適応とされるようになった。 しかし隣接面のクラックやTooth wearなどが原因でう蝕を併発するような疾病構造に変化してきたため、残存歯質の強度を考慮した修復法が見直されることになってきた。 コンポジットレジン修復やインレー修復よりも歯質の破折防止効果に優れ、クラウン修復よりも歯質削除量を少なくする修復法として、オーバーレイ修復が新たに広まりつつある。歯学部の教育や歯科医師国家試験において網羅されていない内容であるため、懐疑的にとらえる先生も多いのではなかろうか。 本書は、「なぜオーバーレイなのか?」「どのような場合にオーバーレイなのか?」「どのように形成し、どのような手順で行うのか?」「接着操作に必要なラバーダム防湿や切削象牙質の処理は?」「接着処理はどうするのか?」という素朴な疑問に対し、フローチャートと照らし合わせた豊富な症例を通して具体的なオーバーレイ修復の実際を詳しく解説されており、まさにオーバーレイの教科書と呼ぶにふさわしい内容である。 各チャプターにおいて一貫してエビデンスレベルでの考察があり、著者の経験に基づく見解があったうえで、実際の症例を明確に提示されているため説得力があり、とても理解しやすい。 また、特筆すべきは、図表や写真がとても大きく見やすいため、解説されている内容が理解しやすい。写真は明確に著者の意図が写し込まれていて美しく画角も規格化されている。手順のフローチャートや症例選択基準のフローチャートは複雑な内容をスッキリとまとめ、臨床現場で見返す際にも役立つと思われる。 読者の理解度や疑問点を想定して先回りしたようなまとめ方がされており、著者である辻本先生の多くの執筆やセミナー講師としての経験を活かした教育者としての一面が現れていると感じる。プライベートセミナーで繰り返し行われているコースをまとめた内容であるため、ブラッシュアップされ明確かつシンプルに記載されている。 オーバーレイ修復は今までに習ってきた修復治療と大きく異なる新手法であるため、細部を学んで取り組む必要がある。その学ぶべき教科書として唯一無二の書籍であるという読後感を添えて、ぜひお勧めしたい。
7つの最新トピックを1冊でゲットできる、「プチ国際歯科大会」 DHが意外と知らない知識をまとめてみた 7人のエキスパートが疑問に答える
井上 和・編著 槻木恵一/塚崎雅之/黒江敏史/西山 暁/ 伊藤創平/常盤 肇/松丸悠一・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 6,600円(本体6,000円+税10%)・128頁 評 者 山本浩正 (大阪府・山本歯科) ピコン! 誰かからメッセージが届く。PC画面を見ると(あっ、私携帯持ってません)、和さん(編著者)から「本を上梓するので書評よろしく〜」みたいなメッセージ。すぐに「了解〜」くらいのノリで返信。でもその数週間後、届いた本を見て愕然とした。和さん以外にも、そうそうたる執筆陣ではないか。各分野のエキスパートでしかも超有名人ばかり。ちょっと腰が引けたものの、自分の勉強のために拝読することにした。 びっくりしたのは執筆陣のネームバリューだけではない。その多彩で深い内容である。「唾液」「骨」「くさび状欠損」「顎関節症」「歯内療法、エンドペリオ」「アライナー矯正」「全部床義歯」という7つの最新トピックを1冊でゲットできるなんてありえない。レストランへ行ってコース料理を頼んだら、アミューズがフランス料理なのに、冷たいオードブルが和食、温かいオードブルが韓国料理、スープが中華で、メインがイタリア料理……みたいな感じだ。いやいやこれだと「誰がメインなのか」で執筆陣が揉めそうだ。紅白歌合戦という例えもいいかもしれない。いろんなジャンルの音楽、しかもその年一番活躍したメンバーが集うではないか。でも白組、紅組に分かれているわけでもないし、ここでも「誰が大トリなのか」で揉めそうだ。やはりその時一番注目されている演者(私を含む)が登壇する国際歯科大会というのがよさそうだ。そう、本書は「プチ国際歯科大会」なのである。 タイトルにあるように“意外と知らない”トピック、“知ってるけれども、質問されたら答えられるかどうか不安な”トピック、“しばらくアップデートしていなかった”トピックに溢れている。読者によって興味のあるところ、不安のあるところは違うと思うが、各トピックは独立しているので、気になるところから読み始めていいと思う。私はPART1を読んだ後、同じトピックのPART2を読むようにした。たとえば,PART1の「唾液」を読んだあと、PART2の唾液に関するQ&Aを読むという具合だ。最初にテストのつもりで、Q&Aを読んでもいい。質問に答えられなければ、PART1をしっかり読み込むというリバース読みもOKだ。 PART1での和さんの解説も要チェック。臨床へつながるように誘導してくれるし、歯科衛生士として各トピックの内容をどう生かすかも暗示してくれる。個人的にはCHAPTER2の「骨」に関する和さんの解説が好みだ。彼女の目は骨代謝の司令塔である骨芽細胞のほうではなく、破骨細胞に向いているように感じる。途中で「なんだか愛らしいですね」という言葉も飛び出すので、ほとんどヘンタイだ(和さんごめんなさい!)。街を歩いていたら、破骨細胞とデートしてる和さんと出会うかもしれない。そんなときには「見かけたよ」とメッセージを送ろう。ピコン!