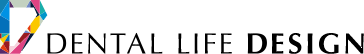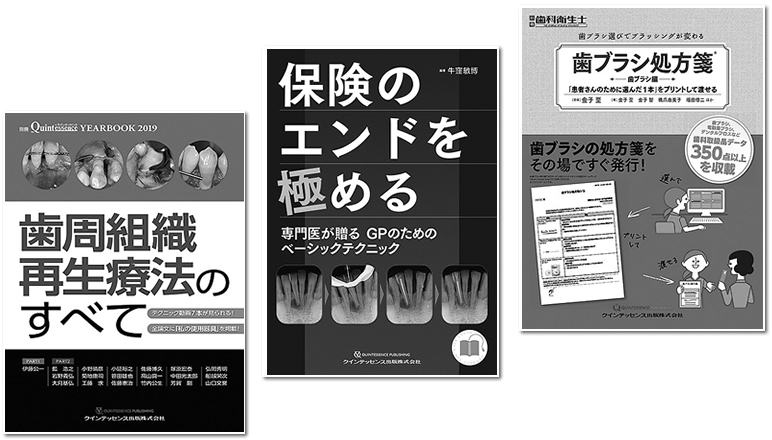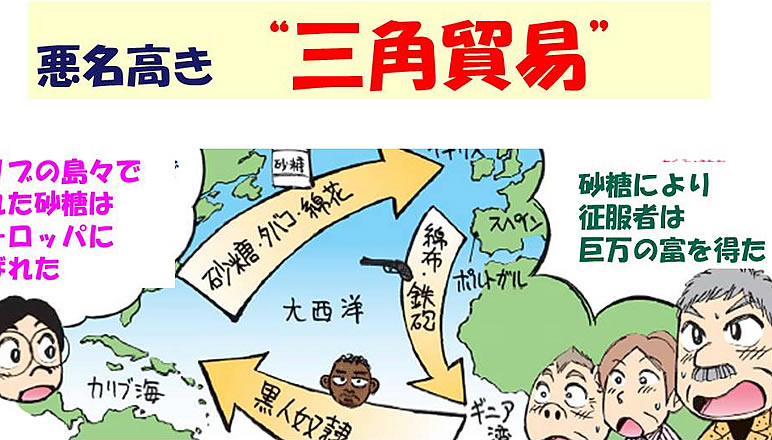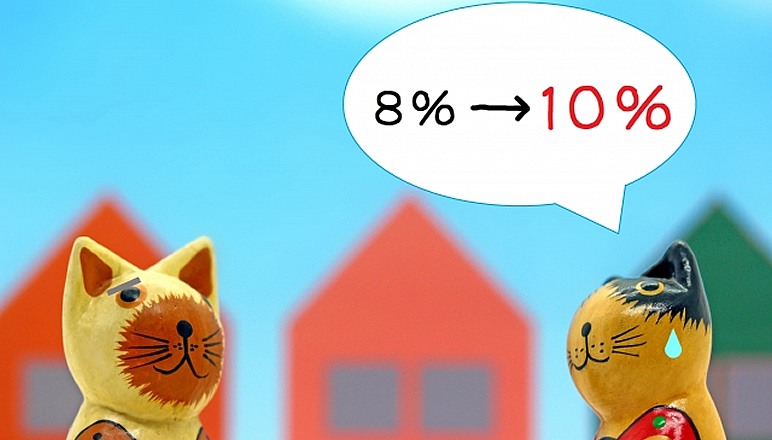「白い歯」を望む患者さんへの治療コンサルツール 別冊ザ・クインテッセンス×nico 白い歯を手に入れたい! ホワイトニング、詰め物、被せ物…… あなたに合った治療の選択ガイド
宮崎真至・監著 木谷 仁/北村 悠/窪地 慶/小峰 太/高田宏起/高野了己/高見澤俊樹/田代浩史/辻本暁正/本田順一/前迫真由美・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 4,950円(本体4,500円+税10%)・88頁 評 者 須崎 明 (愛知県・ぱんだ歯科) 近年、患者の「白い歯」に対するニーズは高まっている。また急速なソーシャルメディアの普及により、「白い歯」について多くの情報を簡単に手に入れられるようになった。一方、そのような流れのなかで、者が多すぎる情報に混乱しているのも事実である。 したがってわれわれ歯科医療従事者には、「白い歯に関する情報」に溺れている患者への手助けが求められる。そうした現状を鑑み、「白い歯を手に入れるためのさまざまな手法」について、豊富な臨床写真をもとにわかりやすく解説しているのが本書だ。 Section1では歯や詰め物の色が変わる原因と、そのおもな治療法についてをテーマとしている。歯の色調の概念にくわえ、一般人を対象とした意識調査の結果なども参考にして、患者自身が悩んでいる色調の変化の原因はどのようなものなのか。またそれはどのような方法で解決できるのかを、術前・術後の写真を用いながらイメージしやすくまとめている。Section1の最後には、「歯の色を改善するフローチャート」が掲載されており、患者自身が希望の治療法を選択する助けとなるよう、またその詳細をあらためて復習できるように配慮されているのも本書の特徴といえよう。 続くSection2では、白い歯を手に入れるための治療法の実例が15種類(ブラッシング、PMTC、オフィスホワイトニング、ホームホワイトニング、デュアルホワイトニング、ウォーキングブリーチ、コンポジットレジン、セラミックインレー、セラミックアンレー、セラミッククラウン、ラミネートベニア、ノンメタルクラスプデンチャー、セラミックブリッジ、接着ブリッジ、インプラント)紹介されている。 術前・術後の写真はもちろんのこと、術中の処置や技工操作などについても詳しく述べている。患者に治療の見えない部分を知ってもらうことは治療の付加価値を上げることにつながり、結果的に自由診療を選択する優位性が高まると思われる。治療により白い歯を手に入れたあとは、その白さを長持ちさせるために定期健診が重要であることを強調している点には、著者らの治療に対する真摯な思いが伝わってくる。 さらに、歯を白くするための治療法がビジュアル的にまとめられている巻末付録「治療の選択 ナビゲーションカード」は、チェアサイドでのカウンセリングに役立つことだろう。 興味があることを調べる際、情報源が紙媒体のみしかなかった時代から比較して、現在はインターネットで検索できるだけでなく、生成AIの進化により短時間で膨大な量の情報が得られるようになった。だからこそいまのわれわれには、患者が消化できないくらいに抱えた情報を、患者ごとに「あなたにはどの情報がふさわしいのか」を整理し個別に提示することが求められている。その際、本書は心強いアイテムとなるのではないだろうか。
シンプルかつわかりやすい最新の知識が身につく,GBRの名著が誕生! ベーシックGBR もう迷わない骨補填材料&メンブレンの材料選択と術式
安斉昌照/中田光太郎・著 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 9,900円(本体9,000円+税10%)・120頁 評 者 松野智宣 (日本歯科大学附属病院口腔外科) こんなコンセプトのGBRの本をいつか作ってみたいと思っていた。しかし、その何倍も素晴らしい出来栄えのこの『ベーシックGBR』を手にしたとき、“誰もが待ち望んでいた、これまでになかったGBRの指南書ができたんだ!”という衝撃を受けた。これまでGBRを躊躇していた方、これからGBRを取り入れたい方、これまでのGBRを見直したい方、さらに、これまでのGBRに満足している方も含め、すべての方々にこの『ベーシックGBR』を迷いなくお薦めしたい。 すでにご存じの方も多いと思うが、著者の一人である安斉昌照先生は、インプラントのみならず歯周外科領域などのセミナー講師や数多くの論文を執筆され、とてもアクティブに活躍されている新進気鋭のドクターである。本学附属病院での勉強会でもほぼレギュラーで講師をお願いしているのだが、センス際立つテクニックと術式選択、それを裏づける臨床結果などを才能溢れるプレゼン能力で解説してくれ、若手医局員にもとても人気がある。そんな私の自慢できる後輩の安斉先生が、彼の師匠であり、昨夏にUrban教授の『Vertical 2 骨造成』で監訳をご一緒させていただいた中田光太郎先生とタッグを組んでまとめられたのが本書である。主な構成としては「GBRの基礎」と「GBRの臨床」の2つにわけられ、A4判・120ページなので、チェアサイドでいつでもすぐに目を通せる。では、何がこれまでのGBR関連書籍と違うのか?各Partの特徴をまとめてみる。 Part1のGBRの基礎では、GBRの基礎知識を身につけてもらうため、わかりやすいイラストや図表、さらに豊富な症例写真を提示して視覚的に、そして参考文献を引用して学術的に解説している。GBRの原理原則、バイオロジー、患者管理、組織・解剖、必要な外科器具、そして、GBRには欠かせない骨補填材やメンブレンなどの材料まで幅広い内容を網羅している。さらに、その解説内容を「簡単に説明すると……」として、Pointをシンプルにまとめているので理解が深まる。とかく、基礎的知識の解説は教科書的に固くなりがちだが、本書では楽しく、面白いようにページがめくられる。何といっても、材料の適材適所の項は必見である。 Part2のGBRの臨床では、後半の約40ページで、Part1で学んだ基礎知識をベースにGBRの臨床が学べる。その主な内容は、切開線のデザイン・剥離のポイント、GBRの術式の選択、減張切開の基本手技、縫合のテクニック、そして術後合併症とその対処法である。とくに、術式の選択では、症例ごとに難易度が二次元展開され、使用する材料の組み合わせも示され、これまでになかった構成となっている。 本書のタイトルは『ベーシックGBR』であるが、GBR未経験者からエキスパートまで、「買って良かった!」と実感できる、まさに“GBRの名著!”なのである。
硬・軟組織マネジメントに定評のある著者陣のテクニックが目白押し! 別冊QDI 外科術式とlongevityから再考するインプラント周囲組織マネジメント オッセオインテグレイション・スタディクラブ・オブ・ジャパン 22ndミーティング抄録集
松島正和・監修 松井徳雄/中村茂人/甘利佳之/飯田吉郎/ 岡田素平太/菊地康司/村川達也・編集 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 6,820円(本体6,200円+税10%)・184頁 評 者 金成雅彦 (山口県・クリスタル歯科) 1986年、米国・カリフォルニア州においてインプラント治療の臨床と教育を目的としたOsseointegration Study Club Southern California(以下、OSCSC)が設立された。OSCSCのリーダーたちとPer-Ingvar Brånemark氏から直接指導を受けた小宮山彌太郎氏と日本の有志のメンバー(現OSCSC会長である山下恒彦氏も含む)によって、日本国内のインプラント治療に携わるスタディグループが垣根を越えて参加協力すべく、オッセオインテグレイション・スタディクラブ・オブ・ジャパン(以下、OJ)が2002年に設立された。OJの目的は、グループ間の交流、情報交換のみならず、互いの研鑽による技術の向上、次世代のインプラントロジストの育成、そして日本におけるインプラント治療の発展に寄与貢献することである。 OJは今年で設立23年目を迎えるが、今期から筆者が12代目の会長に就任させていただいた。一昨年から、理事メンバーは世代交代が進み、次世代のインプラント治療の発展を目指して同世代間の交流を深めていくことが、会長として課せられた責務であると感じている。 本書は、2024年7月27日(土)、28日(日)に一橋大学一橋講堂にて開催された第22回OJ年次ミーティングに登壇された演者の講演内容を集約したものである。この年次ミーティングは、「インプラント周囲組織のマネジメントを再考する」をテーマとして開催された。 書籍の前半は、シンポジウムⅠ「インプラント周囲組織安定を目指したプランニング」、シンポジウムⅡ「外科術式 こだわりを語ろう!」、シンポジウムⅢ「Longevityを実現するためのチームアプローチ」の講演をまとめた内容となっている。インプラント治療を進めるうえで、術前の硬・軟組織や欠損歯数の条件によりどのようにアプローチするか、術前の綿密な治療計画の重要性を語るシンポジウムⅠ。審美領域における硬・軟組織を高度なテクニックを駆使し、いかにマネジメントするかのこだわりを語ったシンポジウムⅡ。そしてシンポジウムⅢでは、インプラント治療のLongevityを見据えて、歯科技工士との連携をいかに綿密にし、上部構造を立ち上げていくかを論じている。 書籍後半は、毎年行われている会員発表と正会員コンテストを中心とした内容となっている。正会員の精鋭らによる発表および講演が収録されているが、誌面から感じていただけるようにいずれもトップレベルの治療内容である。 最後に、チーム医療の重要性を語るうえでコデンタルスタッフの協力を欠くことはできないが、充実したチーム医療の具体例を提示し,誌面を締めくくっている。 今後も、日本におけるインプラント治療の発展にOJが寄与すべく、すべての会員がお互いの尊厳を守り、スタディグループとしての礎を今後も構築していくように祈念したい。
世界で翻訳された口唇美容治療のベストセラー Quint-Med リップス 口唇の美容治療のための 注入テクニック45
Regine Reymond/Christian Köhler・著 五十嵐 一/森本太一朗/近藤尚知/ 森 弘樹・監訳 長尾龍典/脇田雅文/今 一裕・翻訳統括 今井 遊/落合久彦/上妻 渉/大黒英莉/ 髙藤恭子/中島航輝/野尻俊樹/三浦 基/ 毛利国安・翻訳 クインテッセンス出版 問合先 03-5842-2272(営業部) 定価 36,300円(本体33,000円+税10%)・360頁 評 者 根本康子 (東京都・表参道デンタルオフィス) 歯科の臨床において口唇周囲の形成治療は、従来の歯科治療(補綴、矯正、歯周外科など)と併用しその補完として、口元全体の調和の取れた美しさと若々しさの向上が期待でき、審美治療の新たなオプションとなり得る可能性がある。新たな分野の開拓は歯科医師過剰と言われる昨今、歯科医師の多様な働き方にもつながるかもしれない。 しかしながら、この分野は卒後の専門的な技術や経験はもちろんのこと、解剖学的知識を含め多角的な知識が必要となり、不適切な施術は合併症や期待外れの結果を招く可能性があり、患者の信頼を大きく損ねることになる。それゆえ、満足いく結果を安全かつ確実に提供することが求められる。 本書は口唇の美しさに対する多角的な視点と治療アプローチを解説した実践書である。歯科医師にとって有用な実践的知見が満載で、単に審美に特化しているわけではなく、科学的データと解剖学的理解を基盤に、診察、分析、治療において応用可能な具体的手法が提示されている。口唇と顔全体の調和、上口唇と下口唇の比率(黄金比)、プロポーションが与える審美的印象を論じ、これを歯科臨床に応用する指針が提示されており、審美的視点の強化にもつながるであろう。 また、日常臨床において口唇の解剖学的知識が不可欠であることは言うまでもないが、本書では筋、神経および血管についての詳細が図解にて示され、口唇周辺の解剖構造が治療に与える影響を解説している。そのため、局所麻酔や外科手術およびインプラント治療などにおいて安全確実に治療するための解剖書としても活用できる。 さらに興味深い内容として、加齢により起こる口元の変化が皮膚、脂肪組織、筋肉、骨格レベルでどのように進行するかが科学的根拠をもとに詳述されている。その加齢による変化が口元のプロファイルに与える影響を予測できることは、咬合再構築や矯正治療また床義歯補綴などの治療計画を考える際にも役立つのではないだろうか。 実際の注入テクニックの項では、治療技術を細かく分類し、多様な患者ニーズに対応可能な施術法を提示している。とくに、写真や図表、動画を多用しているため、複雑な手技も視覚的に理解しやすく、すぐに臨床応用できる点は、本書の特徴でもある。 加えて本書では、治療ミスや過剰な施術が顔全体に与える影響についても警鐘を鳴らしている。患者の自然な表情を失わせるリスクを十分に留意し、必要最小限の手法で最大の効果を引き出す「バランス重視」のアプローチの重要性を強調している。 「口唇は美の象徴であり、健康や感情の窓である」と本文中に述べられている。本書「リップス」は、歯科医師が審美と機能の観点から、口唇を含めた口腔審美治療の質を高めるための欠かせないリファレンスである。