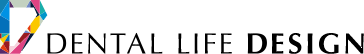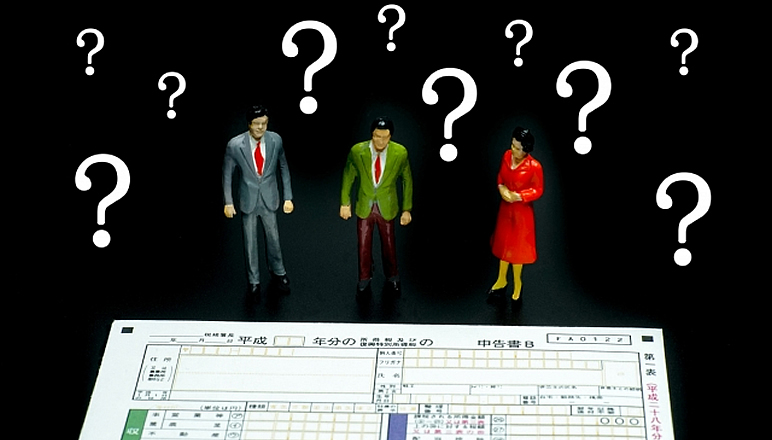病院と在宅での感じる「意思決定支援」の違い
私は、葛飾区にて地域医療に身を置いて一般外来診療と訪問歯科診療を行い、はや3か月が経過しました。最近は特に訪問診療において、病院と在宅とで大きな違いを感じています。 それは「意思決定支援」です。このキーワードは、訪問歯科診療でなくても地域医療を実践する際には避けてとおれない重要なテーマです。今回は、私の急性期・回復期病院での経験をふまえて、多職種連携や在宅医療の現場で歯科医師がどのように意思決定支援に関与し、患者さん・家族・チーム医療に貢献できるのかについて、実臨床の視点から述べてみたいと思います。 意思決定支援とは、患者さんがみずからの価値観や希望に基づき、治療やケアの選択を行う過程をサポートすることです。私は、病院への訪問診療と在宅への訪問診療において、その患者さんが置かれている状況によって想いが異なることを感じます。 急性期病院では、入院時のDisposition(退院後の行き先や療養環境の決定)を主治医が決めますが、そこにはつねに患者さんとその家族の想いが取り巻いています。今後の治療次第で転院か施設か、あるいは自宅か、主治医の判断によって患者さん家族とすり合わすこともあります。その判断を支援する立場として、病院では多職種のコメディカルの中で医療ソーシャルワーカー(MSW)がメインとなります。 また、在宅は病院とは異なり職種も多くはなく、患者さん家族が近くにいることなど、つまり生活が基盤となる点が大きく異なります。 そもそも意思決定に対する支援なので、患者さんの生き方について医療がどこまで介入すべきなのか、よくディスカッションの焦点となることが多いです。ただ、疾患によって多少なりともハンディキャップをもつ患者さんですので、少しでも生き方に対してお役に立てるような伴走するイメージでかかわることが良いのかもしれません。歯科医師における意思決定支援
それでは、歯科医師の意思決定支援に対する関与はどうでしょうか。病院や在宅ともに共通することは、歯科治療を義歯修理や抜歯をつうじて、入院中の経口摂取開始のきっかけや、退院後の食事摂取や嚥下機能を確保できるかという栄養経路の確保であり、それが在宅復帰や施設入所の可否に影響します。 また、歯科医療においては、う蝕治療や義歯作製・修理、抜歯といった治療処置だけでなく、終末期の口腔ケアや摂食嚥下リハビリテーションでの経口摂取の可否について、多職種を巻き込んだ意思決定の場面で、患者さんの意思を尊重した支援が求められます。 つまり、全身状態や生活背景までをトータルでアセスメントし生活に寄り添う、すなわち“Extensivist”としての視点が歯科医師には不可欠です。単に口腔内の状態を診るだけでなく、患者さんの生活の質(QOL)や家族の介護力、社会的背景も含めて、多職種と協働して意思決定を支援することが、これからの歯科医療に求められています(図1)。図1 訪問歯科治療の様子(本人の掲載同意済)。下義歯の残根の保存不可のため抜歯を行う。この1つ意思決定には患者さん本人以外のさまざまな方を巻き込んで説明を行った。
在宅医療・ACPの現場から
超高齢者社会となっている日本において、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)というワードはだいぶ周知されてきました。ACPは「家族会議」と訳されていますが、患者さん本人が将来の医療やケアについて事前に考え、家族や医療者と話し合い、意思を共有するプロセスです。これは患者さんの口から語られる言葉から始まる話合いによって形成されるプロセス(過程)なので、さまざまに変化します。なお、医療でのDNAR(Do Not Attempt Resuscitation)とは異なります。 高齢者の訪問診療が増加するなか、ACPの重要性が高まっています。多職種でかかわる在宅医療については、これをタイムラグなく共有することが重要です。歯科医師がACPに関与する意義
意思決定支援には、ベースにACPがあるといわれています。歯科医師がACPにかかわる意義としては、やはり「食べる」ことではないでしょうか(図2)。摂食嚥下障害や口腔機能低下が、患者さんの生死や生活の質に直結するため、地域医療のチームの一員としては歯科医師側の専門的なアセスメントと提案が必要です。 終末期における口腔ケアの目標設定や、義歯の適応可否の判断など、患者さんの希望と現実的な選択肢を整理し、家族やチームと合意形成を図る役割が求められます。しかしながら在宅医療の現場では、患者さん本人の意思が明確でない場合も多く、家族や多職種とのコミュニケーションをつうじて、患者さんにみずから語ってもらう「本当の想い」を引き出す力が歯科医師に求められます。図2 独居高齢者の訪問歯科治療後、3日目には食事は満足に摂取できたとのこと(本人の掲載同意済)。
実臨床でのポイント
入院早期からの歯科介入:入院直後から歯科医師が院内のチーム医療(NST、摂食嚥下、褥瘡、緩和ケアなど)に加わることで、患者さんの口腔機能を最大限に活かし、より適切なDispositionへの一助となります。 多職種連携:看護師、リハビリ療法士、管理栄養士、医師、薬剤師、MSWと連携し、患者さんの生活全体を見据えた意思決定支援を行うことが重要です。患者本人の意思決定を支えるために
現場で感じるのは、「患者さん本人の意思」が置き去りにされがちな点です。現状として、特に高齢者や認知症患者では、家族や医療者の意向が先行しやすい傾向にあります。しかし、患者さん中心の医療を実現するためには、どんな状況でも「患者さん本人の声」に耳を傾ける姿勢が不可欠です。地域医療で意思決定支援の一助となるために
意思決定支援は、歯科医師にとって単なる「説明」や「同意取得」ではありません。患者さん・家族・多職種とともに悩み、考え、最善の道を探るプロセスそのものです。今後、在宅医療や高齢者医療がさらに進展するなかで、私たち歯科医師が担う意思決定支援の役割は、ますます重要性を増していくことと思います。このような考え方を、他の多くの歯科医療者と共有していきたいと思います。
TOP>コラム>病院歯科から地域へ―開業医からみた病診連携・高齢者歯科医療の実践― 第4回:「意思決定支援」への向き合い方

著者寺中 智
あやせほりきり中央歯科口腔機能クリニック院長(東京都葛飾区)
所属・資格
- 日本補綴歯科学会専門医
- 日本老年歯科医学会専門医・指導医・代議員・理事
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士・評議員)
- 日本有病者歯科医療学会
- 日本プライマリ・ケア連合学会(高齢者医療・在宅医療委員会、生涯学習委員会)
- 日本病院総合診療医学会
- 東京科学大学大学院 高齢者歯科学分野 非常勤講師
- 東京科学大学歯学部附属病院臨床研修歯科医指導医
- 日本ACLS協会BLSインストラクター
- 2003年3月 神奈川歯科大学卒業
- 2003年4月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野
- 2007年3月 東京医科歯科大学大学院修了 歯学博士
- 2007年4月 東京医科歯科大学歯学部附属病院 スペシャルケア外来 医員
- 2010年4月 東京医科歯科大学大学院特任助教 摂食リハビリテーション外来(両兼任)
- 2013年12月 足利赤十字病院リハビリテーション科
- 2020年2月 足利赤十字病院リハビリテーション科 口腔治療室長
- 2024年7月 足利赤十字病院リハビリテーション科 副部長
- 2025年4月 現在に至る 著書に『別冊 ザ・クインテッセンス 病院歯科の現在地』(クインテッセンス出版・共著)がある。
略歴