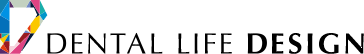地域医療構想がもたらす歯科医療のパラダイムシフト
第1回でもご紹介しましたとおり、第8次医療計画にある地域医療構想に沿った歯科医療の役割の転換期が問われています。今回は、病院と診療所との連携について少し考えてみたいと思います。 地域住民の健康を守るということは、プライマリケアの観点では重要です。Patient Journeyのどの点においても、歯科医療の介入による口腔管理が重要であることは前回述べたとおりです。 地域には医療介護関連の団体が存在し、協働しています。前職の足利赤十字病院では、病診連携・診診連携研修会という研修会を開催していました。地域医療機関(医科と歯科の診療所)と基幹病院との交流を図るための研修会によって、顔の見える関係が構築できるようになります。このように地域の基幹病院は地域医療とつながる機会をつくっています。 また、その研修会のような大きな機会ではなく診療所単位で気軽に情報交換ができる関係も必要のため、かかりつけ医の有無については必ず聞いています。患者さんは、割と当院から近くの診療所にかかっている方が多く、おおよそ2、3軒の同じ診療所に集約されています。そこで私は4月に異動してからは、予約時間が空いた時に電話でアポイントを入れて挨拶に行ったりもしていました。総合病院に「歯科がない」現実と地域医療の課題
診療所を受診している患者さんについては、診療情報提供書のやり取りで情報共有は迅速に行えますが、病院に関しては別に感じます(図1)。大規模な病院ほど、スピード感がやや劣りますが、病態や検査結果など、詳細な情報を提供していただけます。ただ、診療所に比べると病院の方が歯科医療の必要性な度合いが圧倒的に多いと感じています。 なぜなら急性期病院では特に歯科がなく、歯科医療の対応が困難な入院患者が多いからです。義歯修理や抜歯、修復治療はもちろん、摂食嚥下リハビリテーションの観点からも、歯科の早期介入の必要性は多いはずですが、歯科のない病院では、患者さんのQOL向上や医療費抑制の機会を逸している現状があります。図1 診療情報提供書の一例。詳細な血液検査データと処方薬の情報を提供していただいている。
歯科と病院・診療所の連携強化
歯科は、国が示している地域医療構想に沿って単独での診療から病院や診療所との密な連携へと舵を切る必要があります。 たとえば、入院患者の退院後の口腔管理や、在宅療養中の患者さんへの訪問歯科診療は、医科との情報共有が前提となります。特に在宅診療を行うにあたり、処方薬に関してはお薬手帳の処方期間を注意することが必要です。同じ処方とはいえ、処方日がかなり経過している場合、実際は処方変更されていることもありますので、薬局やかかりつけ医に対診を行う必要があります(図2)。また、入院患者のカンファレンスに歯科医師が積極的に参画し、医師・看護師・リハビリスタッフ・管理栄養士・薬剤師と多職種で協働することで、患者さんの全身状態や口腔管理を通して総合的に支える体制が構築できます。図2 薬剤情報の共有の一例(処方日と期間に注目)。
診診連携の深化と地域包括ケアの実践
病診連携の他に診診連携、すなわち歯科同士や歯科と診療所の連携も、今後ますます重要性を増します。患者さんの生活圏に密着した医療提供には、診療所間での情報共有や役割分担が不可欠です。特に、在宅医療や施設入所者の口腔・栄養・リハビリ管理は、歯科がかかりつけ医と連携し、患者さんの生活の質を守る「地域包括ケア」の要となります。そこで、地域の歯科が実臨床でできるポイントを3つ挙げたいと思います。 •退院支援カンファレンス、地域ケア会議など、多職種連携が求められる場に歯科医師が積極的に参加し、口腔管理の重要性を発信する •訪問歯科や在宅医療での医科・介護職との情報共有体制を強化し、患者さんの全身管理に貢献する •地域の病診連携・診診連携研修会や医療連携ネットワークに参画し、歯科の役割を明確にアピールする歯科医療は、“点”ではなく“線”で支える医療へ
地域医療構想時代、歯科医師には「口腔から全身を診る」というExtensivistとしての視点と、多職種・多機関との連携力が求められます。歯科医療は、“点”ではなく“線”で支える医療へ――つまり連携力によって、歯科医療の未来を創っていく必要があります。 病院・診療所との連携を深化させることで、地域住民の健康管理、QOL向上と医療経済の両立を実現し、地域医療の未来が切り拓けると思います。地域医療のハブ的な役割として歯科医療であるべき日は、もうすぐそこに近づいています。

著者寺中 智
あやせほりきり中央歯科口腔機能クリニック院長(東京都葛飾区)
所属・資格
- 日本補綴歯科学会専門医
- 日本老年歯科医学会専門医・指導医・代議員・理事
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士・評議員)
- 日本有病者歯科医療学会
- 日本プライマリ・ケア連合学会(高齢者医療・在宅医療委員会、生涯学習委員会)
- 日本病院総合診療医学会
- 東京科学大学大学院 高齢者歯科学分野 非常勤講師
- 東京科学大学歯学部附属病院臨床研修歯科医指導医
- 日本ACLS協会BLSインストラクター
- 2003年3月 神奈川歯科大学卒業
- 2003年4月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野
- 2007年3月 東京医科歯科大学大学院修了 歯学博士
- 2007年4月 東京医科歯科大学歯学部附属病院 スペシャルケア外来 医員
- 2010年4月 東京医科歯科大学大学院特任助教 摂食リハビリテーション外来(両兼任)
- 2013年12月 足利赤十字病院リハビリテーション科
- 2020年2月 足利赤十字病院リハビリテーション科 口腔治療室長
- 2024年7月 足利赤十字病院リハビリテーション科 副部長
- 2025年4月 現在に至る 著書に『別冊 ザ・クインテッセンス 病院歯科の現在地』(クインテッセンス出版・共著)がある。
略歴