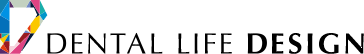シックハウス症候群、発見者は歯科医師
近年、歯科医療は「口腔の健康を守る」枠組みを超え、全身の健康、さらには社会全体のウェルビーイングへとその役割を拡大しています。今回は内容を変えて、社会貢献について述べてみたいと思います。なぜ、急に社会貢献かというと、地域医療に従事することはすでに社会貢献ですが、その枠組みから少し離れた視点での社会貢献が歯科にもあってもいいのではないかと思っているからです。子ども食堂を開設したり、暮らしの保健室を運営したりされている歯科医師の先生方を私は何人か知っています。その中で、シックハウス症候群の問題提起をみずから実践した歯科医師・上原裕之先生をフィーチャーしたいと思います。歯科医療の“社会実装”を意識する本稿では、専門性を活かした社会貢献の可能性を探ります。 皆さん、「シックハウス症候群」という言葉をご存じでしょうか? 歯科医師・上原裕之先生が自身の診療所で発症した体験をきっかけに命名されました。1993年、自宅兼診療所の新築時に、家族やスタッフに目の痛みや気分不良が多発。徹底的な調査の末、建材のホルムアルデヒドによる健康被害と特定し、医療団体や行政へ働きかけるも理解を得られず、最終的には「シックハウスを考える会」を設立して啓発活動を開始。こうしたイノベーティブな視点が、従来の“治療者”としての歯科医師像を大きく変えました。国民会議の創設と住環境への貢献
こうした動きを社会全体へと広げるべく、上原先生が理事長を務める「一般社団法人 健康・省エネ住宅を推進する国民会議」では、消費者、学術、行政、企業横断的なネットワークを構築し、「一部屋断熱」や「生命を守る一部屋確保」といった理念を掲げてシンポジウムや断熱改修の普及活動を展開。特に医師会や住宅関係の団体と連携して、東京都内でデータ収集も行い、住宅の省エネ・断熱性能の向上が真の健康促進に直結するとのエビデンス(参考文献1を参照)を発信しています。 最近、新築のマンションや住宅で目にするZEH(ゼッチ:ゼロ・エネルギー・ハウス)水準の省エネ住宅をご存知でしょうか? ZEH水準の省エネ住宅は、エネルギーの使用量とCO2排出量を削減し、光熱費を抑えながら地球環境にも貢献する住まいです。2030年以降の新築住宅では、ZEH水準の省エネ性能が求められます。その背景として、2021年8月に国土交通省・経済産業省・環境省の3省が「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」を公表しました。2050年カーボンニュートラル達成に向け、世界的に取り組みが進むなかで、2025年には建物の規模に関係なく、すべての新築住宅に対して省エネ基準適合が義務化となります。2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指すという国の政策もあり、現在住宅の販売・賃貸広告に「省エネ性能ラベル」が表示されています。図1 省エネ性能ラベル(国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/shoene-jutaku/より)。
「室温18℃以上」という住宅環境が命を守る
日本の住宅は冬季の室温が10℃台と低いため、ヒートショックによる健康リスクが欧米より高いという現実があります。浴室や寝室での急激な温度差が脳卒中や心疾患発症のリスク因子となる一方、断熱化による在宅改修で血圧が有意に低下した根拠1や、室温が18℃以上の維持は健康長寿に重要とされています。WHOの住宅と健康に関するガイドラインでは「室温18℃以上」が勧告され、日本でも健康住宅が健康寿命延伸に寄与する流れが生まれています。健康日本21(第3次)と住居環境
第3次の「健康日本21」では「他分野や社会的環境との連携」および「個人の健康づくりを支える環境の整備」を推進することが明記されていて、特に、建築・住宅等の分野における取り組みと積極的に連携することでスマートウェルネス住宅などの大規模実証が進み、暖かな住まいが高血圧・脳卒中リスクを低減するなどの知見が蓄積されています。在宅医療に密接に関係する住環境の視点
2040年以降、日本は超高齢社会のピークを迎え、85歳以上の在宅医療ニーズが2020年比で62%増加するといわれ、歯科訪問診療も増えていくなか、「住居環境を医療者がどう診るか」が、患者さんの生活の質や疾患管理に直結する視点となっています。行政も「地域医療構想」策定時に、どの医療機関が在宅や高齢者対応を担うか明確化し、医療・住居連携の促進を打ち出しています。訪問歯科診療も口腔機能の維持のみならず、食支援や誤嚥予防、全身状態の評価を担う専門職として患者さんの住環境を診る視点が重要と思います。 たとえば、訪問診療時にバイタル測定の他に居住空間の室温確認を加えても良いかもしれません(図2)。住環境が良くなければ、美味しく食事も摂れません。特に摂食嚥下障害患者における評価では寒冷環境にいる場合、筋緊張が高まり、普段どおりのパフォーマンスが出ないことも予想されます。図2 訪問診療でも居住空間の状況を見る必要がある(患者さん本人の掲載同意済)。
社会実装のために歯科ができること
これまで上原先生が取り組まれてきたことは、各省庁からの補助金などによって社会実装されています。この規模までは及ばなくても歯科医療としては、臨床現場で得られた「生活者の声」を発信し続けること、健康日本21(第3次)にもあるように「他分野や社会的環境との連携」で多職種連携のハブとして地域に根付くこと、実態データの収集・啓発活動を継続することが不可欠です。 厚生労働省は「在宅医療における医師・歯科医師の定期的な診察と適切な評価に基づく指示」において、住環境評価を明確に推進しており、特に「住環境の整備・改善」(たとえば一部屋断熱やバリアフリー改修)のアドバイスなど必要に応じて多職種(医師、作業療法士、ケアマネージャーなど)だけではなく多業種(住宅改修・リフォーム業者)への橋渡しは、今後重要なことと思います。 歯科医師は「口腔から全身・生活までをトータルで診るチームアセスメントの一員」として、住居環境評価・改善も実臨床の武器となる時代になります。まさに地域医療における「Extensivist」の実現が社会実装になるかもしれません。 参考文献 1.Umishio W, Ikaga T, Kario K, Fujino Y, Hoshi T, Ando S, Suzuki M, Yoshimura T, Yoshino H, Murakami S; Smart Wellness Housing survey group. Intervention study of the effect of insulation retrofitting on home blood pressure in winter: a nationwide Smart Wellness Housing survey. J Hypertens. 2020 Dec;38(12):2510-18.

著者寺中 智
あやせほりきり中央歯科口腔機能クリニック院長(東京都葛飾区)
所属・資格
- 日本補綴歯科学会専門医
- 日本老年歯科医学会専門医・指導医・代議員・理事
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士・評議員)
- 日本有病者歯科医療学会
- 日本プライマリ・ケア連合学会(高齢者医療・在宅医療委員会、生涯学習委員会)
- 日本病院総合診療医学会
- 東京科学大学大学院 高齢者歯科学分野 非常勤講師
- 東京科学大学歯学部附属病院臨床研修歯科医指導医
- 日本ACLS協会BLSインストラクター
- 2003年3月 神奈川歯科大学卒業
- 2003年4月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野
- 2007年3月 東京医科歯科大学大学院修了 歯学博士
- 2007年4月 東京医科歯科大学歯学部附属病院 スペシャルケア外来 医員
- 2010年4月 東京医科歯科大学大学院特任助教 摂食リハビリテーション外来(両兼任)
- 2013年12月 足利赤十字病院リハビリテーション科
- 2020年2月 足利赤十字病院リハビリテーション科 口腔治療室長
- 2024年7月 足利赤十字病院リハビリテーション科 副部長
- 2025年4月 現在に至る 著書に『別冊 ザ・クインテッセンス 病院歯科の現在地』(クインテッセンス出版・共著)がある。
略歴