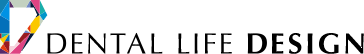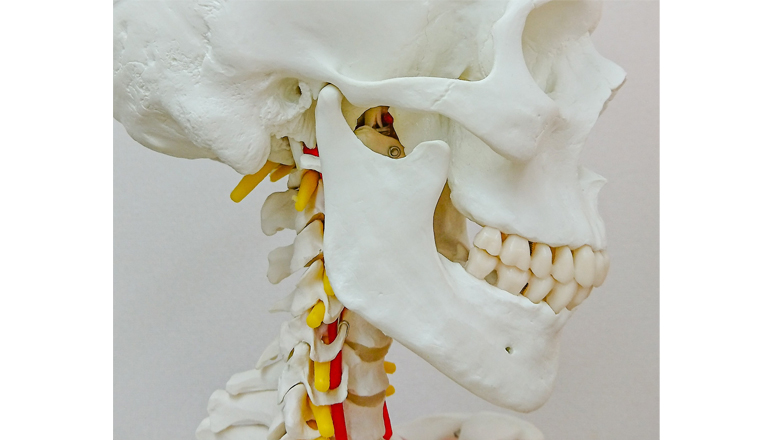小児歯科に特化し、さまざまな取り組みを行う「豊橋キッズデンタルクリニック」。同クリニックの理事長である中野崇先生に、小児歯科を目指したきっかけや、注力する口腔機能発達不全症に対する取り組み、定期的な来院を促す工夫や考え方などについて、また、それらを実践する歯科衛生士の橋本莉菜さんと管理栄養士の望月茜さんにお話を伺いました。 PART1治療を怖がる子どもを見て、疑問に感じ小児歯科の道へ
--中野先生が小児歯科専門医を志すようになった経緯をお聞かせください 中野:子どもたちの成長発達を見ながら医療に携わることに興味があり、治療にも増して、予防や健康増進に重きを置いて患者さんを診ていきたいという希望がありました。卒業間近な時期に、父の知人が経営する歯科医院を見学する機会がありました。そこで、虫歯治療を怖がっている小児患者を見て、「こんなに治療を嫌がる子どもにどうすればできるようになるのだろう…どうしたら予防ができたのだろう」と疑問を感じたことから小児歯科に興味が湧き、大学院に進学しました。 大学院ではやはり虫歯予防に関わることに着目し、極低濃度のフッ化物が歯の脱灰抑制や再石灰化に与える影響について研究していましたが、大学院卒業後は不正咬合の原因と予防について、口腔機能の発達との関係に興味を持って臨床に取り組むようになりました。大学の臨床現場では弁当を持参していただき、実際に子どもに食べてもらい、「食べる機能」・「飲む機能」について評価と支援を行ったり、夏季休暇には、その頃の昭和大学の向井美惠教授・弘中祥司准教授のもとで摂食・嚥下機能訓練について研修を受けさせていただいたりするなど、大学のご協力のもと、口腔機能の発達について勉強を行っていました。その後、地元の福祉事業会の乳児院などで口腔保健支援を行っていましたが、大学に勤務しながら地域医療への貢献を続けるのは難しいと感じ始め、徐々に気持ちが開業に傾いていきました。 -- 実際に開業しようと思われたのは、どんなタイミングだったのでしょうか 中野:もともと大学には長く残りたいと考えており、0歳から第二大臼歯の咬合が完成するまでの患者さん管理をしたいという思いがありました。開業を具体的に意識したのは、外傷で受診された 1 歳の配当患者さんを、担当医として継続して診療し、う蝕予防や治療、咬合誘導など、ひと通りのことを行って、第二大臼歯による咬合が完成する15歳までを見届けることができたあたりだったと思います。その頃には、「食べる機能」・「飲む機能」と不正咬合の結びつきについて、私なりの考え方の基礎が固まったという手応えもあり、定型発達児の口腔機能評価と支援については私が担当し、障害の重い摂食・嚥下障害については医局で共に摂食・嚥下機能障害を診療していた先生に対応を任せると役割分担を決め、2014 年に「豊橋キッズデンタルクリニック」を開業しました。2014年に開業した豊橋キッズデンタルクリニック。
大型駐車場完備の複合文化施設である向山フォレスタ内にあり、遠方からも多くの患者さんが訪れる。
クリニックでは、歯科嫌いにさせない“無理のない治療”を展開
-- クリニックの施設・設備面での特徴を教えてください 中野:当初は1フロアだったのですが、現在は1階と2階の2フロアで展開しており、1階をオープンスクール(親子教室)や小児矯正のアクティビティなどを行う健康増進スペース、2階を診療・予防スペースとしています。診療フロアの中央にはフラットタイプの「スペースラインHPO- 0」を、フロアの両サイドに設けた個室と半個室には背板が起こせる「スペースライン スピリットV」を設置し、歯科衛生士によるメインテナンスの場合はスペースラインHPO- 0、型取りや検査を行う場合はスペースライン スピリットVと使い分けをしています。フラットタイプのシートは、どこに頭を置くかということを子どもが即座に理解でき、治療が終われば背板が起こされるのを待つことなく診療台から降りることができるので、治療がスムーズに行えるというメリットがあります。個室と半個室に関しては、大きな声が出てしまう子どもや、抑制などが必要な場合は個室に、笑気吸入鎮静法を使用するなど、換気への配慮が必要な場合は半個室に案内しています。親子で楽しく学べる専用施設やキッズスペースが整う開放的な1階フロア。同院のマスコットであるフクロウが仲間と住む森をイメージしている

2階の診療フロアにはフラットタイプのチェアユニット「スペースラインHPO- 0」のほか、印象採得や検査用に背板を起こせる「スペースライン スピリットV」を設置。カウンセリングルームやX線室もポップな色合いでまとめ、治療の恐怖を感じることなく受診することができる。
オリジナリティ溢れる診療における特徴
-- 次に、診療の特徴について伺います。月齢・年齢別の治療を行っているとのことですが、その内容をご説明いただけますでしょうか 中野:まず、0〜3歳は、口の中の確認や生活習慣についての健康教育、口腔育成(顔、口のマッサージやブラッシング指導)などを中心に行います。これは、う蝕予防や美しい歯並びへの土台づくりは歯が生える前から始まるためで、保護者には離乳食の進め方や幼児食の考え方、食具の選択についてのアドバイスなど、主に家庭での環境設定と健康教育を行います。 4〜6歳は、治療の簡単な説明(Tell)、使用器具を見せる(Show)、治療を行う(Do)の TSD法で対応し、歯科医院嫌いにさせない、その子に合わせた無理のない診察を行っています。具体的には、口腔内の状態と歯並びの確認、口腔衛生を保つ口腔ケア製品や道具選び、ブラッシング指導・フッ化物塗布のほか、指しゃぶりや舌癖の改善、食べ方・飲み方についての摂食機能指導など、口腔機能の発達支援も行います。 7歳以降は、原因から考えた顎顔面発育不全の評価と小児予防矯正についての説明、(食)生活習慣確認とブラッシング指導・フッ化物塗布、PMTC などを行いながら、自律した口腔衛生習慣を身につけられるようにしています。 -- 歯科衛生士の橋本さんに伺います。処置や指導をする際、特に意識していることや工夫していることはありますか 橋本:処置や指導の際に心がけているのは、子どもの視点で考えること。自分がもし小さい子どもだったら、何をされるかわからないのがいちばん怖いと思うんです。ですから、怖がっている子どもには、これから使用する歯ブラシとミラーを見せて、「今日はこれだけね」と最初に約束します。それでも怖がっていたら手に持って触らせて、「ちょっとお口に入れてごらん」と口に入れさせる。そして、その姿を「お母さんに見てもらおうか」と促し、それができたら「それじゃ、次はお姉さんが見てみるね」と細かく段階を踏むようにしています。それでも泣いて処置が進まない子どもに関しては、経験のある先輩にアドバイスをもらいながら対応したり、場合によっては「歯科慣れトレーニング」に誘導したりします。歯科衛生士 橋本莉奈さん -- 「オープンスクール(親子教室)」もとても人気が高いと伺いましたが、それはどのような形で行われているのでしょうか 中野:機能発達をテーマに、全6回コースで実施しています。クラスは0〜1歳と、2, 3歳に分かれ、いずれも定員6組。内容は10分程度の講和とアクティビティで、各回のテーマに合わせて歯科衛生士、管理栄養士、保育士が順番に講師を担当しています。 -- どのような方々が参加されているのですか 中野:2階の診療に通う患者さんとその保護者です。初診の問診や診療で、生活の中で感じる口の機能に関する不安(食べるスピードや量、お口ポカンや口呼吸など)を保護者にヒアリングし、必要に応じて誘導しています。最近は口コミで情報が広がり、「オープンスクール」に参加するために初診を受ける方もおられます。

取材に伺った際、ちょうど2, 3歳児向けの「オープンスクール」が開催されていた。冒頭に中野理事長が口腔機能や姿勢などに関する講和を行い、その後、歯科衛生士や管理栄養士、保育士がそれぞれの専門知識を生かして、学びと遊びの場を提供している。 -- 管理栄養士の望月さんに伺います。望月さんはどんなテーマを担当されているのですか。また、準備はどのように行っていますか 望月:管理栄養士が担当する回は、食育や生活習慣などで、管理栄養士ならではの知識を生かしたテーマになっています。どのテーマでも、10分間の講話とアクティビティで構成するのですが、講話の内容は、保護者へのアンケートや、私が歯科助手として診療についているときに耳にする保護者の質問などをもとに検討しています。現場で聞く保護者の声は、いちばん新しい生の声。ですから、できるだけ細かく拾い上げ、「オープンスクール」に還元することを意識しています。低年齢を対象とするアクティビティについては保育士にアドバイスを求めるなど、専門職同士の意見交換も活発に行っています。
管理栄養士・歯科助手 望月茜さん -- 管理栄養士から見て、最近の小児の傾向についてはどのように思われますか? 望月:最近の傾向としては、口腔機能が悪く、歯や舌、顎の筋肉をうまく使えていない子どもが増えているように思います。偏食を気にする保護者も多いのですが、子どもたちは味が嫌いなのではなく、噛みこなせない、飲み込みにくいから嫌いということもあるようです。最近では、飲み物をこぼさず飲めるストローマグや、つまんで使用できる柄の短いスプーンなど、一見便利なグッズが販売されており、多くの保護者が使用しています。育児の手間を省くことができる商品だと思いますが、使用時期を間違えると、口の機能の発達に影響を及ぼす可能性があるので、「ストローマグはコップを使って飲む練習を終えてから」など、使い始める時期をアドバイスするようにしています。 -- 「オープンスクール」の他にも管理栄養士が中心になって行っているイベントがあるそうですね 望月:将来、歯周病になる人を減らすことを目的に、理想的な生活習慣やう蝕の原因になりにくい食生活、おやつの選び方などを伝える「ピカピカ教室」を開催しています。具体的には、それぞれ記入してもらった生活習慣シートの内容に沿って良い食生活習慣の目標を設定し、次の来院時に、前回からその日までの生活を振り返りながら目標が達成できたかを確認します。他にも、砂糖に関するクイズや、砂糖がどれくらい入っているかを知るための炭酸ジュース作り体験なども取り入れています。対象は、2階の歯科医院に通う小学生以上の児童と保護者で、参加は希望制ですが、う蝕や歯周病のリスクが高いと思われる児童にはこちらから声をかけ、参加を促すこともあります。 「DENTAL KITCHEN Letter」は、2か月に一度発行していて、私が入職する前から続けられている取り組みです。表面は保護者向け、裏面は子ども向けで、簡単なクイズや迷路などを掲載。セミナーで学んだ食育のことなど、伝えたいことを選んで内容を決めています。管理栄養士3人が交代で担当するので自分の担当は半年に一度です。ホームページに掲載するほか、待合室に配布用として置いています。また、本棚にファイリングしてバックナンバーも見られるようにしています。
「ピカピカ教室」についてのパンフレットと実際の教室の様子。むし歯ができる理由をはじめ、間食(おやつ)などに関するお話や、糖分をテーマにしたクイズなど、さまざまな切り口で子どもたちの学びや気づきを促す。
「DENTAL KITCHIN Letter」。管理栄養士のスタッフが作成を担当し、2か月に1回発行する。食をテーマに役立つ情報を紹介。 インタビュイー 中野 崇(医療法人Bright Beans 豊橋キッズデンタルクリニック 理事長 )/ 橋本 莉奈(歯科衛生士)/ 望月 茜(管理栄養士・歯科助手) 口腔機能発達不全症に対する取り組みと定期的な来院に繋げる創意工夫 PART1 口腔機能発達不全症に対する取り組みと定期的な来院に繋げる創意工夫 PART2

著者中野 崇
医療法人Bright Beans
豊橋キッズデンタルクリニック 理事長
略歴
- 1995年 愛知学院大学歯学部卒業
- 1999年 愛知学院大学歯学部大学院歯学研究科修了
- 2001年 愛知学院大学小児歯科学講座講師(2014 年まで)
- 2002年 愛知学院大学在外研究員(英国 リーズ大学客員研究員 2003 年まで)
- 2014年 豊橋キッズデンタルクリニック開業
- 愛知学院大学歯学部小児歯科学講座非常勤講師
- 豊橋歯科衛生士専門学校講師
- 2022年 朝日大学非常勤教員
- 公益社団法人 日本小児歯科学会:専門医・指導医
- 一般社団法人 日本障害者歯科学会:認定医
- 新進気鋭の小児歯科医 小児歯科に架ける夢を語る, 東京臨床出版, 小児歯科臨床1月号, 2010.
- 小児歯科は成育医療へ, 重症齲蝕が全身に及ぼす影響, 全身疾患と歯質の耐齲蝕, デンタルダイヤモンド(東京), デンタルダイヤモンド春季増刊号, 2011.
- 子どもの歯に強くなる本, なぜ乳歯はう蝕になりやすいか, う蝕になりやすいのはどんな子, クインテッセンス出版(東京),2012
- 乳歯列期における外傷歯の診断と治療 第2版, 治療法の実際,クインテッセンス出版(東京), 2013
- 口唇口蓋裂 Q&A 140, 医歯薬出版(東京), 2015.
- 創造とその表現について, JSPP会員によるリレーエッセイ, 東京臨床出版(東京), 小児歯科臨床10月号, 2015.
- デンタルハイジーン別冊「子どもの対応まるわかりブック」医歯薬出版(東京)P.97,109,2017.
- 歯科医院スマート化ガイドブック 2nd」kira books(横浜)P.72-75.2017.
- 第56回日本小児歯科学会大会 自由集会「これからの咬合誘導を考える」過蓋咬合. 東京臨床出版(東京)小児歯科臨床11月号. 2018.
- 第57回日本小児歯科学会大会 ② 顔面の成長に焦点を当てたBiobloc療法を成長期に行う意義, 小児歯科臨床 2019年12月号, 東京臨床出版(東京)2019
- いつ、なにをやる?ライフステージで考える小児期の口腔管理, the Quintessence. Vol.41. クインテッセンス出版株式会社(東京)2022.
- 臨床の玉手匣(エクラン) 小児歯科編, Chapter 8-1:歯科で行う食育, デンタルダイヤモンド社(東京)2022.
書 籍(分 筆)
略歴