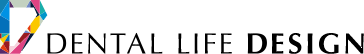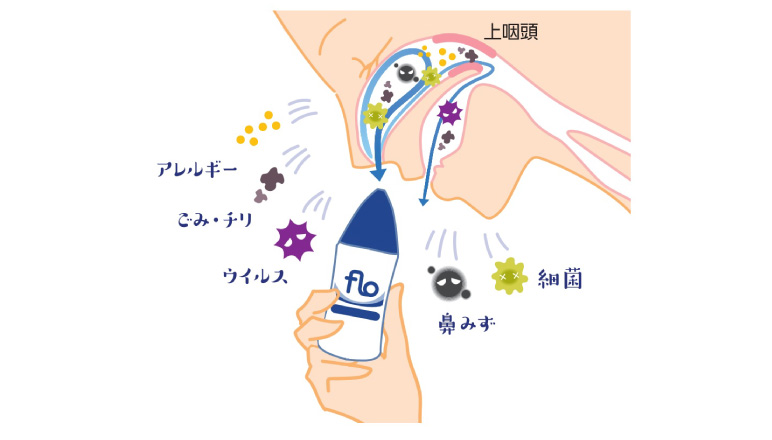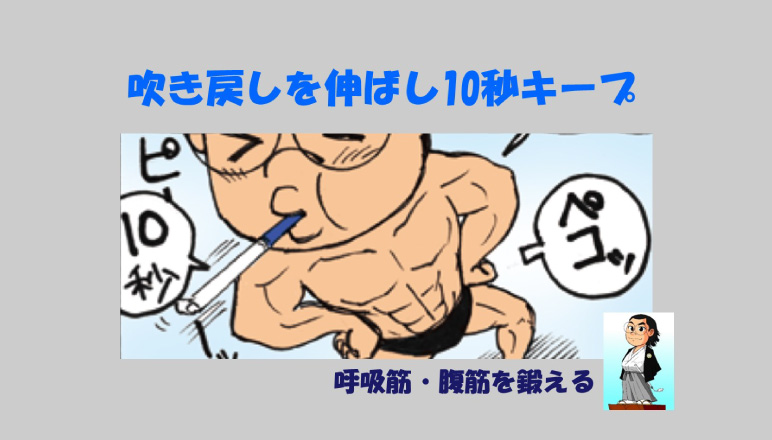2月上旬、今季最強で最長の寒波が、大雪、低温、強風を日本列島にもたらしていた。依頼を受けていた福岡での講演会の準備をしながら、ずっと天気と交通機関の状況を気にかけた。 講演当日、午前中の診療を早めに切り上げて駅へと向かう。道すがら路肩に車を寄せ、スマホで新幹線の遅れを確認し、講演開始予定時間から逆算して何とか間に合うはずだと心を落ち着かせる。自分の力では何ともできないこと、似たようなここちを何度か味わってきた。 約80分の遅れで博多駅に降り立った。改札口を目指しながら地下鉄に乗ろうかとも考えたが、会場近くで迷うことを恐れタクシー乗り場へと急いだ。しかし、駅出口まで来るとすぐに乗り場に続く長蛇の列が目に入ったため、予約済の駅前のホテルにチェックインし、タクシーの手配をお願いすることにした。 タクシーに乗り込むと、運転手が「今日はアイドルグループと米津玄師のライブがあるので、ホテルは空いてないし、タクシーも捕まらないでしょう」と話し始めた。最近のアーティスト事情に疎い私でも、米津玄師は知っている。取り止めのない会話を交わしながら彼の「Lemon」の曲を浮かべていた。 講演会と懇親会を終えた翌日、目覚めるとすぐに「父母ヶ浜(以下、浜)にゴミ拾いに行こう」と体を起こした。日課とは恐ろしいものである。ホテルにいることに気づき、もう一度ベッドに潜り込んだが、目を閉じていると、浜の情景と先日観たマイクロプラスチックについて取り上げた番組が思い出された。その内容は衝撃的なものだった。 まず、富士山での調査で大気中にマイクロプラスチックが含まれていることが示されていた。それは私たちが呼吸しながらマイクロプラスチックを取り込む可能性を示唆している。また、すでに昨年日本でも、献血採取された血液内からマイクロプラスチックが確認されている。 さらには、University of Campania Luigi Vanvitelli(イタリア)のRaffaele Marfella氏らの研究も紹介されていた。頸動脈疾患の患者257人の血管にできたプラーク(塊)を切除して分析したところ、約60%から直径5ミリ以下の「マイクロプラスチック」などの微小プラが検出された。そして、頸動脈プラークからマイクロプラスチックまたはナノプラスチック(MNP)が検出された患者は、検出されなかった患者と比較して、追跡34ヵ月時点の心筋梗塞、脳卒中、全死因死亡の複合リスクが4.53倍と有意に高かったことが示されていた。 マイクロプラスチックの主な供給源は、漂流ごみとして問題となっている劣化したプラスチック製品、それを日課である浜で毎日拾い上げている。帰って浜に行こうと荷物をまとめ始めた。 帰宅せず浜に行くと潮が引いていたので、車に携帯しているシューズに履き替え、スーツ姿のままでゴミを拾うことにした。点在する漂着ごみの中で最初に目を引いたのは黄色い檸檬、昨日のタクシー内での会話の影響でもなかろうにと苦笑いをしながら、それをしばらく眺めていた。そして檸檬を見ると、酸蝕症を思い浮かべるのは職業病といえるのかもしれない。 世界中でいちばん多い疾病はう蝕である。2016年の研究では、世界の24.4億人に未処置永久歯う蝕があり、それは世界の人口の35.9%であると報告されている。日本においては、子どもや若者でう蝕は減っていることを強調しがちだが、人口の多い中高年に歯が残ることによってう蝕は増加傾向にある。日本人の約3割が未処置う蝕を有していて、これは世界を対象とした研究から導き出された割合と同等である。すなわち日本では約4,000万人が未処置う蝕を有していて、よく耳にする「糖尿病は予備軍を含めて2,000万人」の数字の倍なのだ。口腔の健康が全身や健康寿命に及ぼす影響を考えれば、その数字を行政、議会、市民へもっと強くアピールすべきだといつも思っている。 中高年層に残存歯数が多くなることによって、破折や咬耗そして酸蝕症を目にする機会は年々多くなっている。当地が柑橘類の産地であることもその要因かもしれないが、健康志向で体にいいと聞くとそれに飛びつく患者が一定数いる。極端な患者になると「歯より体の健康の方が大事」といい、聞く耳をもたない。酸性度の高い飲食物を摂り続ける患者に「歯は体の一部ではないのか」と尋ねたくもなる。 砂浜に残った檸檬は、害を与えることなくやがて自然に帰っていく。檸檬を残したまま、その周りに散らばる劣化しつつあるプラスチックごみを懸命に拾い始めた。とにかく今地球は、汚染、気候変動、生物多様性喪失という3つの危機に晒されているのだ。

著者浪越建男
浪越歯科医院院長(香川県三豊市)
日本補綴歯科学会専門医
略歴
- 1987年3月、長崎大学歯学部卒業
- 1991年3月、長崎大学大学院歯学研究科修了(歯学博士)
- 1991年4月~1994年5月 長崎大学歯学部助手
- 1994年6月、浪越歯科医院開設(香川県三豊市)
- 2001年4月~2002年3月、長崎大学歯学部臨床助教授
- 2002年4月~2010年3月、長崎大学歯学部臨床教授
- 2012年4月~認定NPO法人ウォーターフロリデーションファンド理事長。
- 学校歯科医を務める仁尾小学校(香川県三豊市)が1999年に全日本歯科保健優良校最優秀文部大臣賞を受賞。
- 2011年4月の歯科健診では6年生51名が永久歯カリエスフリーを達成し、日本歯科医師会長賞を受賞。
- 著書に『父母ヶ浜2000日』(近著)をはじめ『季節の中の診療室にて』『このまま使えるDr.もDHも!歯科医院で患者さんにしっかり説明できる本』(ともにクインテッセンス出版)がある。
- 浪越歯科医院ホームページ
https://www.namikoshi.jp/