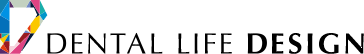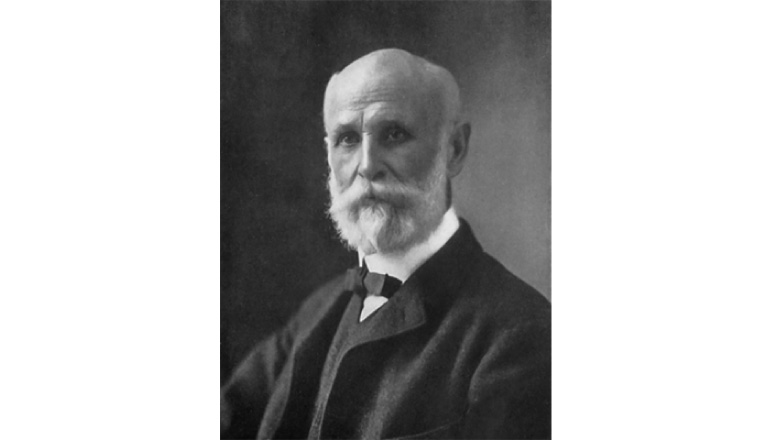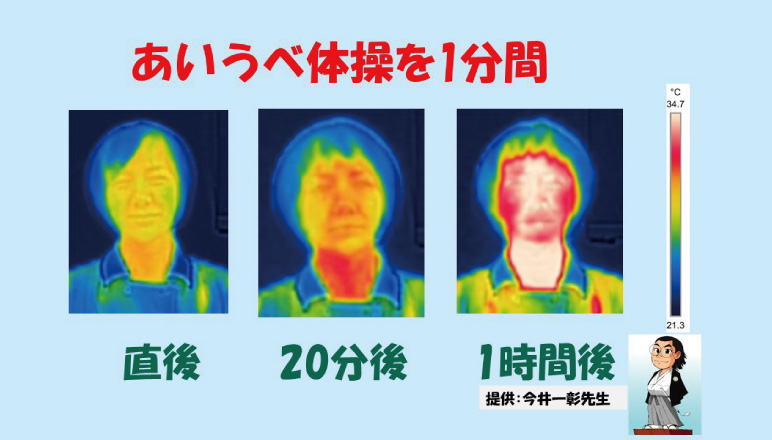臨床医学雑誌の最高峰である「The Lancet」により組織された認知症専門家の委員会が、認知症の予防と介入に関する最新のエビデンスを提示しています。認知症のリスクファクターを語る上で、逃してはならない情報でしょう。 Livingston G, Huntley J, Liu KY, Costafreda SG, Selbæk G, Alladi S, Ames D, Banerjee S, Burns A, Brayne C, Fox NC, Ferri CP, Gitlin LN, Howard R, Kales HC, Kivimäki M, Larson EB, Nakasujja N, Rockwood K, Samus Q, Shirai K, SinghManoux A, Schneider LS, Walsh S, Yao Y, Sommerlad A, Mukadam N. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet. 2024 Aug 10;404(10452):572628. 2024年に更新されたこの報告では、認知症の修正可能な(modifiable)リスクファクターとして14の要因が特定されています。そしてそれらのリスクファクターを解消することで、人口全体の認知症発症率がどれほど減少する可能性があるかを推定する指標が示されています。分析の結果、14の修正可能なリスクファクターをすべて排除した場合、認知症症例の約45%が予防可能であると推定されました。これは、認知症の約半数が、ライフスタイルや環境要因の管理によって発症リスクを減少させる可能性があることを示唆しています。 その14のリスクファクターとそれぞれの寄与率は、以下の通りです。 幼少期 低学歴(5%) 中年期 難聴(7%) 高LDLコレステロール(7%) うつ病(3%) 頭部外傷(3%) 身体活動不足(2%) 糖尿病(2%) 喫煙(2%) 高血圧(2%) 肥満(1%) 過度の飲酒(1%) 高齢期 社会的孤立(5%) 大気汚染(3%) 視力低下(2%) 歯周病や歯の喪失が認知症を誘発すると信じている人にとって、この中に歯科疾患が含まれていないことは意外に思えるかもしれません。確かに、いくつかの観察研究では、歯周病と認知機能の低下との関連が指摘されていますが、これはあくまで相関関係であり、因果関係が証明されているわけではありません。 関連性があるからといって、その疾患や状態が認知症を誘発するとは限りません。他の要因(例:高血圧、糖尿病、喫煙など)が共通して存在し、それらが両方の疾患の発症に寄与している可能性も考えられます。そのため、因果関係を明確に証明するためには、より厳密な研究が必要です。 さらに、14の認知症リスクファクターの中にも、因果関係が完全には証明されていないものがあるのですが、それでも歯科疾患がリスクファクターとして採用されなかった理由が説明されています。 14の認知症リスクファクターは修飾可能であり、介入によってリスクを減少できる可能性が示されているものです。例えば、社会的孤立、視力低下、うつ病などは、たとえ因果関係が完全に証明されていなくても、社会的活動の促進、視力矯正(眼鏡や白内障手術)、うつ病治療(薬物療法・心理療法)といった介入によって、少なくとも認知機能の維持につながる可能性があるため、リストに含まれました。 歯周病や歯の喪失の場合、口腔ケアの改善や歯の保存が認知症リスクを低減するという強固なエビデンスが不足しています。つまり、介入試験(ランダム化比較試験など)で、歯科治療が認知症の発症を予防することが示されていないのです。例えば、現在のところ、義歯の装着と認知症リスクの低減との因果関係を示す決定的な研究結果は存在していません。 また、14の認知症リスクファクターは、認知症との関連性が非常に強く、多くの研究で一貫した結果が示されているものです。例えば難聴と認知症の関連は多くの疫学研究で強く示されており、メタ分析でも認知症リスクが約2倍に増加することが報告されています。視力低下は今回の改訂で新たにリスクファクターとして追加されましたが、視覚情報の減少が脳の刺激低下を招き、認知機能の低下につながるメカニズムがある程度示されました。 一方、歯周病や歯の喪失の場合は、観察研究では関連性が示されているものの、研究によって結果がばらついており、統一的な見解が得られていません。因果関係が証明されていないリスクファクターの中でも、歯科疾患は認知症との関連性が特に不明確な部類に入ると考えられます。 そして、歯周病や歯の喪失は、多くの交絡因子と深く関連しているため、真の因果関係を証明するのが難しいことも理由にあります。例えば、低学歴・低所得の人々では、 •口腔ケアが不十分になりやすい •歯科医療アクセスが限られている •食生活が不健康になりがち といった要因が独立して認知症のリスクを高めている可能性があります。 また、高齢者では、すでに認知機能が低下している人ほど口腔ケアを怠りやすくなり、歯を失いやすいという逆因果関係の可能性があります。つまり、「歯を失ったから認知症になった」のではなく、「認知機能が低下したから歯を失った」可能性があるわけです。 このように、歯周病や歯の喪失は、多くの社会経済的・健康的要因と絡み合っているため、真の因果関係を特定するのが難しいという問題があります。しかし、今後、歯周病治療や義歯装着が認知症の予防に寄与することを示す質の高い研究が蓄積されれば、将来的にリスクファクターとして認められる可能性はあります。 まとめると、歯周病や歯の喪失は認知症と関連性がある可能性は指摘されているものの、因果関係は証明されておらず、逆因果や交絡因子の影響を排除できていないというのが現在の科学的立場です。歯科医療従事者としては、「歯周病や歯の喪失が認知症を誘発する」と断定するのではなく、「関連性が示唆されているが、因果関係は証明されていない」という慎重な姿勢をとるべきでしょう。

著者西 真紀子
NPO法人「科学的なむし歯・歯周病予防を推進する会」(PSAP)理事長・歯科医師
㈱モリタ アドバイザー
略歴
- 1996年 大阪大学歯学部卒業
- 大阪大学歯学部歯科保存学講座入局
- 2000年 スウェーデン王立マルメ大学歯学部カリオロジー講座客員研究員
- 2001年 山形県酒田市日吉歯科診療所勤務
- 2007年 アイルランド国立コーク大学大学院修了 Master of Dental Public Health 取得
- 2018年 同大学院修了 PhD 取得
- NPO法人「科学的なむし歯・歯周病予防を推進する会」(PSAP):
http://www.honto-no-yobou.jp
https://www.instagram.com/psap_2018/
https://www.facebook.com/yobousika
https://twitter.com/makikonishi