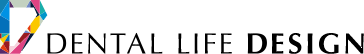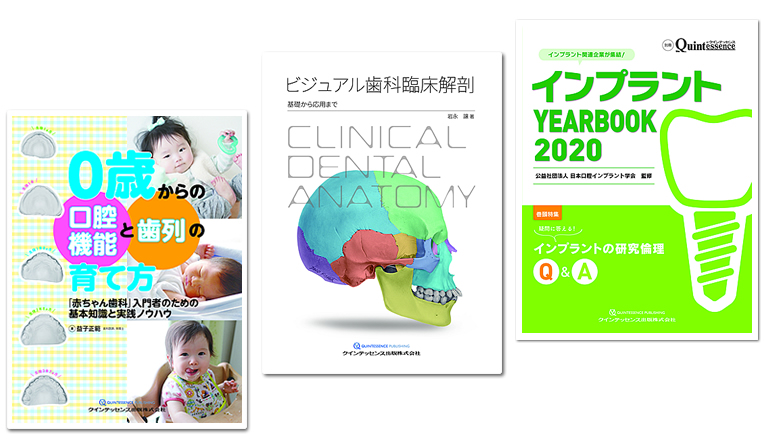昨年、口腔機能発達不全に対する公的医療保険の導入が認められた。これがきっかけで、小児の口腔機能に関する講演会や出版物が急増している。 しかし、ほとんどの保護者は、我が子に咀嚼・呼吸・発音などに問題があるとは思っていないし、子ども自身も自覚症状を訴えない。 発達期において、これらは生涯の健康を獲得するうえで重要な問題である。 そこで、小児の口腔機能発達不全について述べてみる。 さて、筆者が口腔機能発達不全について、始めて耳にしたのは30数年前のテレビ番組である。
当時、TBSテレビの"報道特集"という番組で、キャスター堂本暁子氏(元参議院議員・千葉県知事)が"かめない子"の問題を取り上げた。 1983年、全国4935カ所の保育園で約40万人の園児を対象に"噛むことに問題のある子"について調査した。 調査の結果、 ・「固形物を噛むことができない」 ・「固形物を食べると口から吐き出す」 ・「飲み込むのが下手」 ・「固形物をそのまま飲み込む」 ・「軟らかいものしか食べない」 ・「いつまでも口にため飲み込まない」 ・「しゃべる時,舌の使い方が下手」 などの問題が浮かび上がってきた。
さらに約4割の保育園が、5年前・10年前に比べ"噛むのが下手な子が増えている"と回答していた。 すると保育関係者から、「うちの保育所にもいます・・・」いう問い合わせがテレビ局や保健所に殺到した。 まさに、この番組こそ口腔機能発達不全がクローズアップされるきっかけになったのだ。
また、"子どものからだのおかしさ"について経年的に調べている日本体育大学(子どものからだと心・連絡会議)の調査結果をみると、1990年度に保育士の59.4%が、"最近、咀嚼力が弱い子が増えている"と感じていた。 しかも、これは1979年には見られなかった項目である。
ちなみに、同年の小学校の養護教諭に対する調査結果では、1990年第4位に"歯並びが悪い"が増加したと感じている。
ではどうして、保育士がこの問題に最初に気がついたのだろう? 続く

著者岡崎 好秀
前 岡山大学病院 小児歯科講師
国立モンゴル医科大学 客員教授
略歴
- 1978年 愛知学院大学歯学部 卒業 大阪大学小児歯科 入局
- 1984年 岡山大学小児歯科 講師専門:小児歯科・障害児歯科・健康教育
- 日本小児歯科学会:指導医
- 日本障害者歯科学会:認定医 評議員
- 日本口腔衛生学会:認定医,他
歯科豆知識
「Dr.オカザキのまるごと歯学」では、様々な角度から、歯学についてお話しします。
人が噛む効果について、また動物と食物の関係、治療の組立て、食べることと命について。
知っているようで知らなかった、歯に関する目からウロコのコラムです!
- 岡崎先生ホームページ:
https://okazaki8020.sakura.ne.jp/ - 岡崎先生の記事のバックナンバー:
https://www3.dental-plaza.com/writer/y-okazaki/