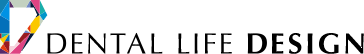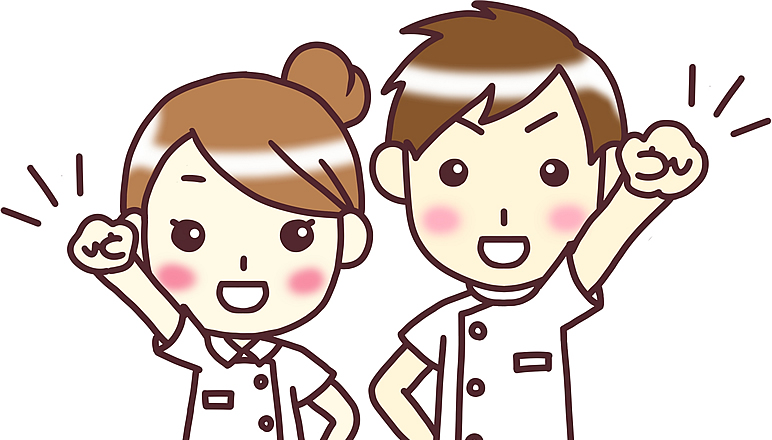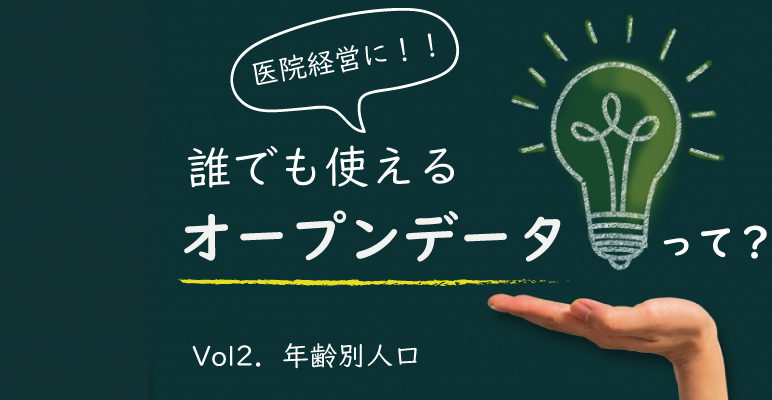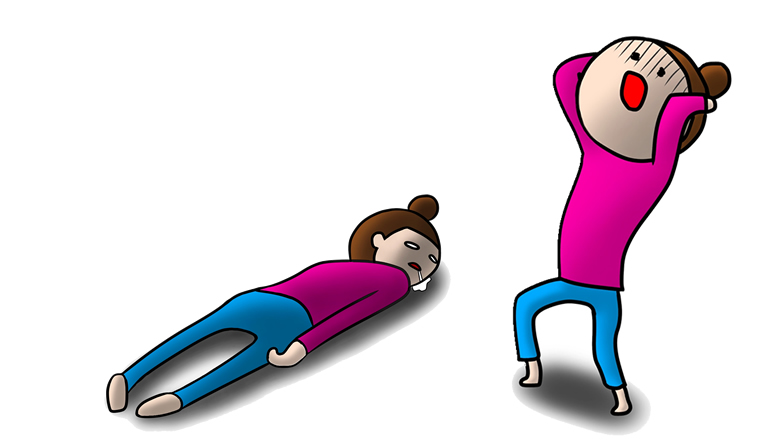歯科医院の集患・増患は、さまざまなツールを使って行います。 適切なツールを選び、効果的に新患、またリピート患者を集めていきましょう。 今回は、患者さんの来院までの流れやオンライン・オフラインそれぞれの集患・増患ツールについて解説します。まずは患者さんが来院するまでの行動を理解
適切な集患・増患を行うために、まずは来院までの行動を押さえておきましょう。 患者さんは、基本的に6つのステップを踏んで来院します。 ※途中のステップを飛ばしたり順番が前後したりする場合もあります。 ⒈ 症状や悩みが起こる ⒉ 症状や悩みの解決方法を調べる ⒊ 歯科医院で解決できることを知る ⒋ 解決するために歯科医院を探す ⒌ 気に入った歯科医院を見つける ⒍ 日程を決めて来院する 大切なことは、数多くある歯科医院の中から「この歯科医院に通いたい!」と思ってもらうこと。 そのために自院のことを知ってもらう必要があります。 しかし、そもそも知る機会がなくアピールできていない歯科医院がほとんどです。 まずは認知してもらうために、また予約につなげるために、さまざまなツールを活用していていきましょう。 【関連】歯科医院における増患対策とは?減患原因や対処法を具体的に解説! 【関連】現役歯科医師に学ぶ!歯科医院の集客(集患)の極意歯科医院の集患ツール【オンライン/ウェブ編】
今や国民の94.8%は、スマートフォンからインターネットにアクセスしています。 【参照】情報通信機器の保有状況|総務省情報通信機器の保有状況|総務省 この患者層を取り込むべく、これから紹介するツールを利用して、オンライン・ウェブでの集患に取り組みましょう。
公式ホームページ
公式ホームページは、歯科医院の看板です。 公式ホームページを持っていないと「ちゃんと運営していない歯科医院なのかな」と疑われることもあるため、特別な事情のない限り、制作をおすすめします。 ホームページには、診療時間や診療科目、診療方針、院内設備、スタッフなどの基本情報を載せておきましょう。 ほかの歯科医院と差別化できる強みがある場合は、しっかりとアピールします。 予約システムを導入しておくと、そのまま予約にもつなげることも可能です。 ただし、SEO対策(インターネットの検索結果で上位に表示される対策)ができていなければ、ほとんどページにアクセスされないこともあります。 「新宿 矯正」といった「場所+診療科目」のキーワードで上位表示できるようにしておきましょう。 自力でSEO対策を行うにはかなりの労力がかかるため、SEO対策を専門で行っている制作会社に依頼することをおすすめします。 【関連】歯科医院にホームページは必要?作成メリットや注意点や費用を解説ポータルサイト
ポータルサイトとは、全国にある歯科医院をまとめて掲載した情報サイトのことです。 基本的にポータルサイトを運営する制作会社がSEO対策をしているため、検索結果では個人のホームページより上位表示されることが多い点が特長です。 掲載する情報は、診療時間・診療科目・電話番号・アクセス・ホームページのURLなど。 ほかの歯科医院と似通った内容になってしまいますが、歯科医院の詳しい紹介ページを作成しているポータルサイトもあります。 費用は、制作会社によって異なります。 たとえば、基本情報を無料で掲載して、追加の紹介ページやポータルサイトからの予約受付を有料としているケースなどがあります。ウェブ広告
SEO対策をしなくとも、費用をかければホームページを上位表示できるツールが広告です。 主なウェブ広告として「リスティング広告」や「ディスプレイ広告」などが挙げられます。 リスティング広告は、インターネットの検索結果に表示される広告で、ユーザーを絞り込んだ検索キーワードを指定して広告を出稿することが可能です。 たとえば、「銀座 ホワイトニング」なら「銀座周辺でホワイトニングのできるクリニック・歯科医院を探している方」に絞って訴求できます。 費用は、ユーザーが表示された広告をクリックするたびに発生します。 1クリックあたり数十円〜数百円が平均で、人気キーワード(検索数が多いキーワード)の場合は千円を超えることもあります。 ディスプレイ広告は、ウェブサイト − 例えばニュースサイトの脇などに表示される広告です。 広告を表示するユーザーを地域・性別・年齢・時間帯などの条件で指定できますが、検索キーワードとは関係なく広告を表示するため、検索型よりクリック率は低くなります。 特定の患者さんではなく、歯科医院の存在を広く一般に知ってもらうために効果的な広告であると言えるでしょう。 広告費用は安く、1クリックではなく1表示ごとに発生します。1表示あたり1円未満〜1円ほどが平均です。 【関連】ウェブマーケティングのプロに聞く!ネットを活用した集客の極意〜その③WEB広告編〜SNS運用
TwitterやInstagramなどのSNSで情報を発信している歯科医院もあります。 一方通行的に情報を発信するだけでなく、口コミ・拡散などで多くのユーザーに歯科医院を知ってもらうことができたり、ユーザーと直接コミュニケーションを取れる点がメリットです。 歯科医院の公式アカウントのみならず、歯科医師の個人アカウントとして運用しても構いません。 歯科医院についてのお知らせを発信することが一般的ですが、歯科に関するハウツー・お役立ち情報を発信しても面白いかもしれません。 ユーザーにとって有益な情報を発信していると、ファンがつきやすく拡散されてより多くの方に知ってもらえます。 注意点として、発信内容によってはユーザーから反感を買い「炎上」してしまう恐れもあることを覚えておきましょう。 炎上で信用を失ってしまうこともあるため、発信内容には注意が必要です。予約受付システム
公式ホームページ上に予約システムを導入しておくと、患者さんの満足度も上がり、またスタッフが電話で予約を受け付ける手間も省けます。 主婦やビジネスマンは、忙しい合間をぬって歯科医院に通います。 「できるだけ短時間で診療を終えたい」「待ちたくない」と考えるため、予約受付をしている歯科医院は喜ばれるでしょう。 注意点として、完全予約制を採用すると「予約が面倒くさい」「予約しても行けるかわからないから、予約したくない」という違うニーズの患者さんを取りこぼしてしまいます。 任意で選べる予約受付制度にすることをおすすめします。オンライン診療
「足腰が弱くて通えない」「家事や仕事で忙しい」という患者さんに喜ばれるのが、オンライン診療です。 2019年度末から世界的に流行した新型コロナウイルスなどの感染症の影響もあり、対面ではなくオンラインでの診療を希望される方も増えています。 新たな集患・増患のツールとして期待できるでしょう。 ただし、「ITツールの操作が苦手」「Wi-fi環境が整っていない」という方には適さない場合もあります。歯科医院の集患ツール【オフライン/リアル編】
オフライン・リアルの集患ツールは、インターネットの苦手な方や診療圏で生活している方へ効果的に打ち出せます。
交通広告
電車やバスなどの交通機関に飾られる広告を交通広告と言います。 交通機関を利用している方への広告になるため、その方の生活圏に歯科医院がないと来院につながりにくいです。 歯科医院の近くを通る電車やバスを狙って、掲出してみましょう。 基本的には、広告代理店を介して広告を出します。 広告代理店は、広告の制作から掲出まで対応してくれます。 交通広告を行う代理店、もしくは交通機関に問い合わせてみてください。ビルボード
ビルの壁面や屋上など街中で見かける看板広告で、交通広告と同じく地域性の強いものです。 駅前や待ち合わせスポットなど、人の集まるエリアに広告を出せば、多くの方の目につきます。 長期間にわたって掲示すると、何度も看板を見てもらうことによる「刷り込み効果」を期待できるでしょう。 ただし、多くの情報を載せることはできないため、情報発信ではなく歯科医院のブランディングや認知に効果を発揮します。 地域の条例で、サイズ・色使いの制限をかけられることもあるため、確認が必要です。DM・ポスティング
診療圏の住民に効果的な集患ツールです。 自宅から通える距離にあっても、通勤・通学・買いものなどで付近を通らない限り、存在を知られていない歯科医院もあるでしょう。 そういった場合に役立つのがDM・ポスティングです。 生活の導線に関係なく、診療圏の住民に知ってもらえます。 制作時には広告内容をしっかりと読んでもらい、来院につながる工夫を行うことが大切です。 また、既存の患者さんにDMを送ってリピートを促すことも効果的であると言えます。折り込みチラシ
新聞の折り込みチラシを利用します。 新聞を購読している世帯にチラシを配るため、若年層よりも年配層向きの広告です。最適なツールを選んで集患・増患を
利用できるツールの種類は多くあります。 集患・増患したい患者層を踏まえて、効果的なツールを活用しましょう。 若年層や利便性を求める患者さんを狙うならオンライン・ウェブのツール、年配層や診療圏の患者さんを狙うならオフライン・リアルのツール、といった具合です。 歯科医院の状況に応じて最適なツールを選ぶことをおすすめします。